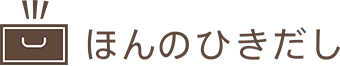3月15日(水)に発売された、冬野岬さんの『毒をもって僕らは』。第11回ポプラ社小説新人賞特別賞受賞作である本作は、SNS社会を生きる不遇な高校生たちが、「生きる証」を打ち立てようともがき苦しみながら駆け抜ける姿を、生々しい筆致で描いた物語です。
今回はそんな本作について、編集を担当したポプラ社の野村浩介さんに文章を寄せていただきました。
『毒をもって僕らは』は突風のようなデビュー作
よくある余命ものね、という思いこみはあっという間に吹き飛ばされ、足場がゆらぐ。態勢を整え直そうとしても、そのままぐいぐい引っ張られてしまう。新人賞の選考過程で勢いのある作品にめぐりあえた。冬野岬の『毒をもって僕らは』という小説だ。
「木島ってさ、六十歳くらいで孤独死しそうな顔をしているな」――。そんなふうにクラスメートに言われてしまう少年が、この小説の主人公。16歳の誕生日に彼が病院で「尿路結石」という年齢に似合わぬ宣告を受けるところから話は始まる。勉強はだめ、将来の夢もない、趣味は心霊動画を見ることくらい。
そんな冴えない高校生・木島に声をかけてきたのが、綿野という同世代の少女だった。不治の病とたたかう彼女は、一癖も二癖もある女の子で、「ねえ、君にお願いがあるんだ」と木島につめより、「この世界の、薄汚い、不幸せなことを私に教えてくれないか」と頼む。
このふたりを軸に回転するストーリーには、生への執着と憧れが渦巻いている。滑稽で、ときに甘美。深夜の学校のトイレ、病室の空調の気配、夏の夜の黒い人波……いくつもの光景が夕暮れの忙しさで飛び去っていく。うんざりするほどの時代の毒にまみれて倒れそうな主人公を、綿野は「嘘はいらない」と突き放す。
だが、どんなに正直に伝えようとしても、まとわりつく嘘をどうしたらいいのだろう? 自分の吐き出した言葉に逆襲されて倒れ、また立ち上がる。言葉の隙間をかいくぐるように進む高校生たちの必死さに、しまいに泣けてしまうのだ。そうとしか生きられないなら、そのように生きてやる――そんな覚悟の深さに胸を揺さぶられる。
「ああ、面白かったなあ」と独りつぶやいたとき、目のあたりが異様にひりひりしていた。目をあけっぱなしで読んだのだろうか。第11回ポプラ社新人賞特別賞受賞作、面白いです。どうぞお楽しみください。
(ポプラ社 編集者 野村浩介)
あわせて読みたい
・文庫化で再注目!イタくてヤバイ生徒と先生のバトルを描く破格の青春小説『二木先生』の魅力