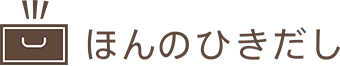9年ぶりの単行本となる『残月記』で2022年本屋大賞7位入賞を果たしたほか、第43回吉川英治文学新人賞と第43回日本SF大賞で、史上初のダブル受賞を達成するなど、独自の物語世界が注目を集める小田雅久仁さん。そんな小田さんが、10年以上の歳月をかけて編んだ作品集が、7月に発売された『禍(わざわい)』です。
本作のテーマは「怪奇」。口、耳、目、肉、鼻、髪、肌といったヒトの〈からだ〉をモチーフに、さまざまな「恐怖」と「驚愕」が繰り広げられます。そんな本作はどのように生み出されたのか、小田さんにたっぷりとお話を伺いました。

小田雅久仁
おだ・まさくに。1974年宮城県生まれ。関西大学法学部政治学科卒業。2009年『増大派に告ぐ』で第21回日本ファンタジーノベル大賞を受賞し、作家デビュー。2013年、受賞後第1作の『本にだって雄と雌があります』で第3回Twitter文学賞国内編第1位。2021年に9年ぶりとなる単行本『残月記』を刊行し、2022年本屋大賞ノミネート、第43回吉川英治文学新人賞と第43回日本SF大賞のダブル受賞を果たす。
- 禍
- 著者:小田雅久仁
- 発売日:2023年07月
- 発行所:新潮社
- 価格:1,870円(税込)
- ISBNコード:9784103197232
恋人の百合子が失踪した。彼女の住むアパートを訪れた私は、隣人を名乗る男と遭遇する。そこで語られる、奇妙な話の数々。果たして、男が目撃した秘技・耳もぐりとは、一体(「耳もぐり」)。ほか、『残月記』で第43回吉川英治文学新人賞受賞&第43回日本SF大賞受賞を果たした著者による、恐怖と驚愕の到達点。
(新潮社公式サイト『禍』より)
「怪奇」をテーマにデビュー第一作を含む全7編を収録
――収録作の「耳もぐり」はデビュー後第一作ということで、『禍』は小田さんのキャリアとともに編まれた作品集となりますね。「耳もぐり」はどういったきっかけで生まれたのでしょうか。
「小説新潮」から、ファンタジー企画をやるので、何か書いてみないかというお話をいただいたことがきっかけです。僕は2009年にデビューしていて、「耳もぐり」はその2年後の2011年に初めて雑誌に掲載していただいた短編でした。
「耳もぐり」がファンタジーというよりは怪奇小説風な作品だったので、同様に体の一部をモチーフにして何編か書けたら、一冊にまとめられるだろうと書き継いでいきました。
――取り上げるパーツとストーリーは、どのようにできていったのですか?
まず耳から始まったので、顔のパーツは押さえておきたいと思いました。口、鼻を書いて、頭にあるので髪も入れたいなと。肉と肌の話は、思いついたので書いてみました。
――「耳もぐり」は失踪した恋人の行方を追い、彼女が住むアパートを訪れた「私」が、彼女の隣人を名乗る男から耳もぐりという秘技について聞かされる話です。
子どもの頃に、手塚治虫さんの『火の鳥』という漫画を読んでいて、事故死してサイボーグとなった男と、女のアンドロイドの精神が融合したロボットが出てきたんです。その話が心に残っていて、いつかそういう精神が融合するような話を書きたいなと思っていたことを覚えています。
「耳もぐり」を書いたのは10年以上前になりますので定かではないですが、そういったSF的なアイデアを、ファンタジーやホラーといった科学的ではない書き方で料理しようと考えたときに、このような話が生まれたのではなかったかと思います。
自分で踏み荒らしていない所を探して作品を書く
――一冊にまとめるにあたって改稿もされているとのことですが、各作品を改めてお読みになっていかがでしたか?
書くときはおもしろいと思えるアイデアから使っていきますし、何作か書いていくにしたがって、「これは前にも使ったな」というアイデアや展開も出てきてしまいます。最初のほうが伸び伸び書いていたなと感じています。
後になるにしたがって、以前はこういう状況になると右に進んでいたけれども、今度は左に行ってみようかと、自分で踏み荒らしていない所を探して作品を書く必要が出てきます。最後に書いた「喪色記」は目の話ですけれども、そういう意味では一番苦労した作品かもしれません。
――ファンタジーやサスペンス、ホラーなどさまざまな要素を併せ持つ作品はそのように生み出されたのですね。「喪色記」は視線への苦手意識を抱え、日々を何とかしのいできた28歳の男が主人公です。男は少年時代から度々見る“滅びの夢”にさいなまれてきましたが、ある日、夢の中で何度も会話を交わしてきた少女が大人になって、彼の“目”から忽然と現れるという幻想的な世界観の作品です。
そういう意味では、不満や劣等感を抱えていたり恵まれない状況にあったりする主人公が、非日常的なことに巻き込まれて、最後はとんでもないところに行ってしまうという部分は共通しているかもしれません。意識していたわけではないのですが、全体を俯瞰した時に、そういう流れになっている作品は多いですね。
自然とそうなるということは、僕自身がそういう作品が好きなのかもしれません。
――「喪色記」は特に世界の終末が舞台となっているので、「破壊と創造」という印象が強くありましたが、それぞれの作品がまったく違う世界を描きながら緻密に構築されていて、短編とは思えないほどのスケールの大きさを感じました。
「髪禍」や「裸婦と裸夫」なども、一つの世界を作って、それを最終的に壊すところまでを一編の中で描いていますので、パニック映画のようなスケール感を感じていただけるのではないでしょうか。
これも僕自身の好みでもあるのですが、日常的なところから話を始めて、主人公だけでなく読者のことも、最終的にはまったく違う景色の中に連れて行きたいという気持ちがあります。その気持ちが反映されて、結果的に“とんでもない終わり方”の作品も出てきていると思います。
――同時に本作の怖いところは、主人公たちにとってこれが果たして禍なのか、ディストピアともいえる世界観に読み手も取り込まれてしまうようなところではないかと感じました。
客観的に見るとひどいことになっているのだけれど、主人公の精神状態もあって、主観的にはそう不幸には感じられないということもあるでしょう。むしろ、それが一番怖い終わり方なのかもしれませんね。
「髪禍」は、特にそういう作品だと思います。

“ノンストップ”な勢いと、パニック映画のようなスケール感を表現
――「髪禍」では、「壊れかけた人生」を生きてきた女が、10万円の報酬を目当てに、“惟髪(かんながら)天道会”と名乗る宗教団体の儀式にサクラとして参加することになります。そこで悪夢そのものの状況に遭遇するわけですが、怒涛のような破壊力のある作品ですね。
映画などでもそうですが、短い時間の中で起きる話は、勢いがつきやすいように思います。「○○時間」といったタイムリミットを感じさせるタイトルの映像作品もありますが、ノンストップで一直線で進んでいくようなスタイルは、小説でも映像でも人気がありますよね。
「髪禍」も主人公が迎えのバスに乗ったら、最後まで脇目も振らずに一直線という話になっています。最後に収録されている「裸婦と裸夫」もそうですが、短時間の間に一気に進んでいく話は、自分でも勢いを感じながら書いていますし、読者にもその勢いに乗って読んでもらえるのではないでしょうか。
――言葉による作品でありながら、スペクタクルというか、壮大な映像が目に浮かぶようでした。小田さんはこれまでのインタビューでも、「映像に負けたくない」という思いを語っていらっしゃいますね。
映画やドラマ、漫画、ゲームなど直接的な映像表現を前にすると、小説はだいぶ分が悪いなあとは思いますが、私は自分の頭の中に、まず視覚的におもしろいと思える光景を思い描いてから、それに向かって書いていくところがあるんです。
同じように、読者の頭の中でもそういう光景が広がっていてほしいなという気持ちを持っています。それを文章でどこまで表現できるかと考えると、無力さを感じる部分はありますが、がんばって何とか食らい付いていきたいですね。
――「農場」は、宿なしの若者が謎の老人にスカウトされて、“農場”とよばれる施設で働くようになる物語です。ただ、そこで植え付けているのは「鼻」であり、収穫する作物が実は……という展開で、この作品などは思い描きたくなくてもつい絵が浮かんでしまったのですが(笑)、どういった映像から生まれたのですか?
まず「鼻」の怪奇小説を書くと決めて、鼻なら何をされたら一番嫌かなと考えたときに、わりとすぐに思いつきました。しかも、その結果の「鼻」が一つだけではインパクトがないので、たくさんの鼻がどうなっているのかを思い描いてある装置が生まれて、と一つひとつ想像を膨らませていき、あの形になりました。

『禍』はタイトルの“究極系”
――小説好きにとって、抗いがたい魅力があるのが「食書」ですね。小説家の男が、本屋の横にあるトイレの引き戸を開けると、女が本のページを破りとって食べていた、というシーンから始まる作品です。本作では、「私がやりたかったのは確かにこういうことだ。小説という巨大な手を伸ばし、読者の心をむんずと鷲づかみにし、荒々しく振り回し、高だかと持ち上げ、強かに叩きつける」いう一文が書かれていますが、小説家としての小田さんの思いでもあるのかなと感じました。
そうですね。そうできたらうれしいですし、自分自身も小説に気持ちを掴まれて振り回されたいと思いながら読んでいます。ですので、小説家としての言葉でもありますし、一読者としての言葉でもあります。
――今回の作品集は「驚愕」や「恐怖」が描かれているのと同時に、登場人物のモノローグに何ともいえないおかしみがあるのも魅力です。主人公が「食書」へと自分で自分を追い込んでいく言葉の連なりは、特に読み応えがありました。発売前には、「小説という手法で『怪奇』を描くことに意義を求めるならば、まずは登場人物の『驚愕』を丁寧に言葉にしてゆくということになろうかと思い、本作品集を執筆するうえで、こだわり続けた点でもありました」とコメントを出されています。
その点は難しいところでした。現実には起こりえない話を書いていますので、人間がそういう状況に陥った時に、どういうふうな反応をするのかは想像するしかありません。頑張って書いたつもりではありますが、同じようなことが実際に誰かの身に降りかかったら、それどころの反応ではないかもしれないですね(笑)。
特に“肌”がテーマの「裸婦と裸夫」などは、怪奇小説というよりはユーモア小説というか、ファンタジーの要素が強い話になりました。
――「裸婦と裸夫」は感染者に触れるとたちまち脱衣衝動に見舞われる病が流行し、大混乱に陥った電車内から抜け出した主人公がビルの屋上へと逃げ込む話です。感染すると、誰もが着ているものを脱ぎ捨ててしまう、という奇病はどういったことから発想されたのでしょうか。
思いついたのはあまりにも前のことできっかけは思い出せないのですが、なかなかそのアイデアを形にできずにいました。結局「服を脱ぐだけでは終わらない」というアイデアを思いついた時に、これで形にできるなと、やっと書くことができた作品です。
――作品集としてのタイトルは『禍』ですが、タイトルはすぐに決まったのですか?
最初は収録作のうちのどれかをタイトルにしようかと思ったのですが、担当編集者からのアドバイスもあり、別の案を考え始めました。
2作目の『本にだって雄と雌があります』の刊行時に取材をしていただいた際は、タイトルが長くてだんだん作品名を言うのが恥ずかしくなってしまったんです。その経験から、タイトルは短くまとまっているほうが言いやすいなという思いがありました。漢字一文字のタイトルは、その究極系ですね。
禍という字は重ねると「禍々しい」になりますし、収録作の「髪禍」にも含まれています。インパクトもあり、怪奇小説的でもありますので気に入っています。
――表紙もかなりのインパクトがあります……。
漢字一文字のタイトルなので、表紙にも大きく配置されるのだろうなと半分は予想していたのですが、文字自体がこんなにおどろおどろしいものになると思ってはいなかったです。予想外でしたが、かっこいいですよね。
タイトル自体が『禍』ですし、もしかすると手にするのを躊躇される読者もいらっしゃるかもしれませんが、そこは怖いもの見たさで(笑)、ぜひ手に取っていただければと思います。

〉〉新潮社公式サイト:「耳もぐり」全文公開・コミカライズはこちら
関連記事
・「この著者、まさしく文藝界の“禍”になる」との推薦コメントも!小田雅久仁さん『禍』:発売に先駆けてコミカライズもスタート!