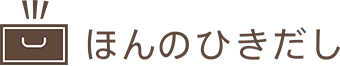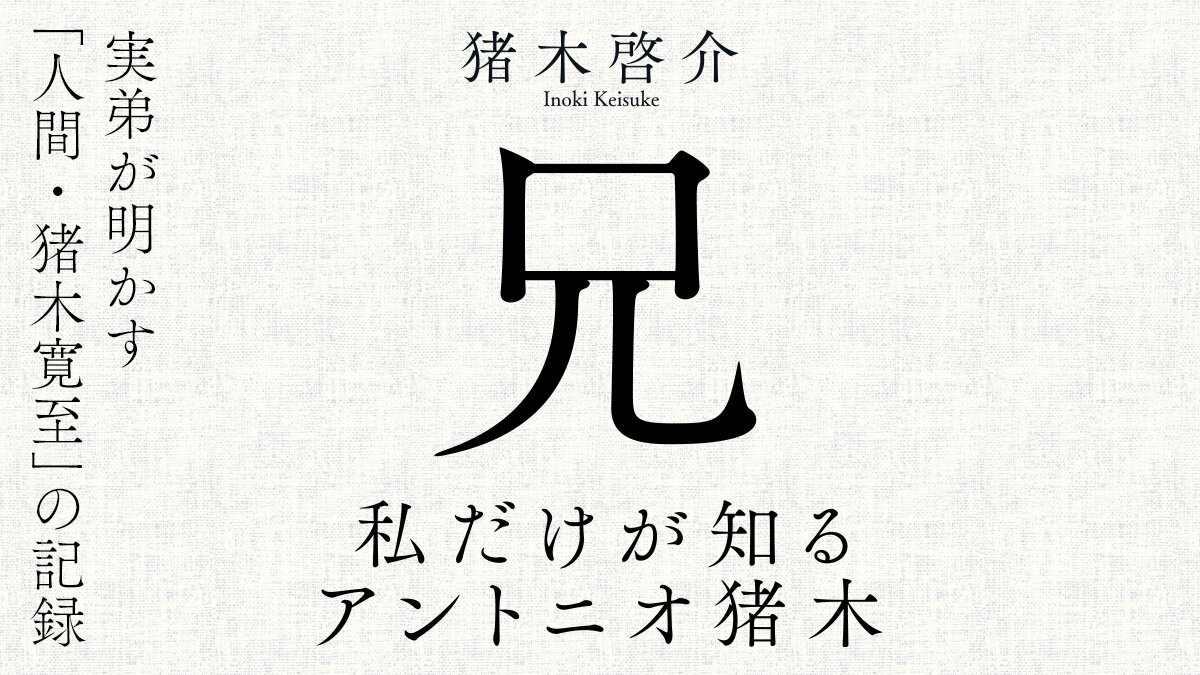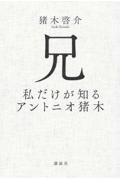「オリンピックに出たいんだ」
突然、途方もない夢を語り出したことに私は言葉を失ったが、兄貴はさらに意外な構想を語り出した。
「オリンピックでメダルを取れば、有名になれるだろう。そうしたら、プロレスラーになれると思うんだ」
思わず、聞き返した。
「プロレスラーになるの?」
兄貴は、ただ小さく頷(うなず)くだけだった。
家族でブラジルに移住する前、砲丸投げの練習に打ち込みながら、まだ何者でもなかった猪木寛至少年は、弟にプロレスラーになる夢を語っていた……静かな感動に包まれる一場面である。
本書は、アントニオ猪木(1943~2022)の実弟・猪木啓介氏による、唯一無二の家族の物語だ。誰もが知る稀代のスーパースターにして、誰にも理解の及ばない深遠なパーソナリティーを抱えた“怪物的巨人”――そんな兄の肖像を、肉親でしか捉えられない視点から綴った「人間の記録」は、これでもかというほど濃密かつ説得力に満ちている。
抑制のきいた筆致には、一般読者も振り落とさない理性と知性が漂う。業界風に染まりきっていない常識人としてのスタンスと、ブラジル育ちのビジネスマンとして生き抜いてきたタフネスが、本書に風通しの良さを与えている。もちろん、プロレスファンが読んでも無類の面白さは確実に味わえるはずだ。
全章・全ページが見どころと言っても差し支えないが、前半の見せ場は、おそらく初めての視点とディテールをもって語られる横浜での少年時代、ブラジルでの苦難に満ちた農場生活だろう。遠い異国の地で、17歳の寛至少年はプロレス界の大スター・力道山にスカウトされ、ほかの兄弟たちもそれぞれの道を歩んでいく。この家族の群像劇も、激動の時代に生きた移民一家のドラマとして、映画化してほしいほど味わい深い。
やがて時は流れ、いよいよプロレスラー・アントニオ猪木の時代がやってくる。ジャイアント馬場と組んだ“BI砲”タッグの台頭、倍賞美津子との結婚、日本プロレスからの追放、新日本プロレスの創設、手探りの旗揚げ戦……読みながら目まぐるしい展開に圧倒される。そして、大学編入のために日本に帰国していた著者も、なし崩し的に新日本プロレスへの参画を求められ、思いがけない兄との二人三脚・第二部が幕を開ける。
まず強烈なインパクトを与えるのが、1971年12月7日、札幌市中島体育センターでの出来事。アントニオ猪木の日本プロレス時代最後の試合に、いきなり呼び出された著者は、会場に着くやいなやユセフ・トルコ氏からナイフを手渡される。
トルコさんは、私に折り畳み式のナイフを手渡した。小型だが、開いてみると刃先は鋭く光る、本物のナイフだった。
「今日の試合、ババとイノキは負けるだろう」
不穏な空気を察した私は、ひたすらトルコさんの話を聞くしかなかった。
「試合が終わる。その後、イノキは仲間から襲われるかもしれない。そうなったら啓介、リングに走って兄貴を救うんだ」
この業界では何が起きても不思議じゃない、という「洗礼」としては十分な出来事だったろう。そして、新日本プロレス発足後の1973年に起きた新宿伊勢丹襲撃事件の現場にも、著者は居合わせていた。新宿の路上で「兄貴」がタイガー・ジェット・シンらに白昼堂々襲われるという光景を、一緒にショッピングを楽しんでいた兄の妻・倍賞美津子とともに、彼は何も知らずに目撃することになる。
事件が演出だったとしよう。それならば、絵を描くことができるのはアントニオ猪木本人しかいない。そして、私や美津子さんは一切、事前に襲撃が起きることなど知らされていなかった。
アントニオ猪木という人間の計り知れなさは、肉親をも翻弄した。むしろ実の弟も本気で慄(おのの)かせるぐらいショッキングな演出でないと世間は驚かない、というバロメーター的存在だったのかとすら思ってしまう。そんな「兄貴」の性格を、著者も時を経るごとに深く理解していく。
やがて「兄貴」はリング上のみならず、経営者としても破滅的なまでの大仕掛けを畳みかけていく。本書はさまざまな事例を通して、その「猪木イズム」の途方もなさを映し出す。いまにして思えば先駆的な、しかし無謀極まりなかったバイオテクノロジー事業「アントン・ハイセル」の推進にも、著者は深く関わっていた。その知られざる詳細を、破綻の原因まで含めて当事者が語った内容は、貴重なものと言えよう。
この事業の難航とも密接にかかわる、あるターニングポイントとして描かれるのが、1983年6月2日の「猪木舌出し失神事件」……ハルク・ホーガンとの一騎打ちで、アックス・ボンバーの直撃を食らった猪木はそのまま場外でダウン。ただちに救急車で東京医大病院に運ばれ、なぜか数時間後にはこっそり代官山の自宅マンションに戻った夜にも、著者はずっと「兄貴」のそばにいた。ブラジル仕込みのドライビング・テクで、猪木夫妻を載せた営業車をぶっ飛ばしたのは、ほかならぬ著者であった。
あのときの兄貴がどれだけ追い詰められていたか――本当に理解が及んでいた人は、私を含めおそらく誰もいなかったと思う。特にハイセル事業の苦しみを共有していた私からすれば、兄貴がリングでテロリズムを決行したのは「プロレスのため」ではなく、自分自身の存在意義を確認するための、たったひとつの選択だったとしか思えない。
(中略)
「お前ら、俺抜きでやれるもんならやってみろ!」
あの日、私が心のなかで聞いたものは、兄貴の「魂の叫び」だったと思うのである。
同情と共感、何より「兄貴」への愛情に溢れた分析には、時に辛辣なまでの率直さ、鋭さも備えている。その冷静な観察眼は、当然、周囲の人間関係にも向けられる。
なぜ兄貴の周囲にいる人間は離反するのか。選手しかり、フロントしかり、あるいはビジネス上のパートナーしかり、アントニオ猪木を取り巻く人間は必ずと言っていいほど離合集散を繰り返す。どうしてそれが起きるのかといえば、兄貴の持って生まれた性格を周囲が誤解しているからである。
アントニオ猪木はスター選手であるが、いわゆる「親分」ではない。リングの上では相手の持ち味を引き出し、最高に輝かせることを得意としたが、団体の経営者として部下の能力を引き出したり、人材を育成しマネジメントする力はまったくゼロ。あくまで自分は神輿(みこし)の上に乗っているだけで、自分のために尽くしてくれる籠をかつぐ人、ワラジを作る人の心の内側には、なかなか思いが至らない人間だった。
むしろ、アントニオ猪木という強力な恒星によって、負の側面や狂気を引き出されてしまったような人々も本書には数多く登場する。著者が穏やかで落ち着いた人柄であることは読んでいて伝わってくるが、そんな著者の平常心を粉砕するような人物との戦いが、本書後半のヤマ場となる。
私はかつて、親しい知人の前でこう言ったことがある。
「もし、あの女に何も天罰が下されないのなら、俺はもう神というものを信じない」
彼にここまで言わせてしまう人物の行状とはどんなものだったのか? 本当に背筋の凍るような内容だが(こういう人、いる!という生々しい実感を誘うところがまた恐ろしい)、それでも最後は救いを感じられる内容になっているので、猪木ファンは安心してページを進めてほしい。その一方、著者を「啓ちゃん」と呼び、現在も親しくしているという倍賞美津子が、終章に再び登場する場面も胸を打つ。
最後に、この本の舞台裏を、魅力たっぷりに語ったくだりも引用しておこう。ここで聞こえてくる「兄貴」の声にしびれたら、もう読まないわけにはいかないはずだ。
余談になるが、本書の企画は佐藤秘書の告発キャンペーンを展開した『週刊現代』(講談社刊)編集部からの提案だった。30年前に「反猪木」の論陣を張った雑誌が、今度は身内である私の本を出すというのだから、「闘魂」を標榜した兄貴もびっくりの「商魂」だが、私はそれも何かの縁だと思っている。
兄貴はいま、こうつぶやいているだろう。
「おもしれえじゃねえか。啓介、俺の名前で本が売れるんだったらどんどんやれよ」
*
(レビュアー:岡本敦史)
- 兄 私だけが知るアントニオ猪木
- 著者:猪木啓介
- 発売日:2025年02月
- 発行所:講談社
- 価格:1,980円(税込)
- ISBNコード:9784065389775
※本記事は、講談社BOOK倶楽部に2025年3月18日に掲載されたものです。
※この記事の内容は掲載当時のものです。