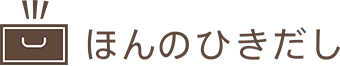“夫婦脚本家”として、「やっぱり猫が好き」「すいか」「野ブタ。をプロデュース」「セクシーボイスアンドロボ」「Q10」など数々の人気ドラマを手がけてきた木皿泉さん。
本屋大賞第2位に輝いたデビュー小説『昨日のカレー、明日のパン』から5年、待望の2作目となる『さざなみのよる』が、4月18日(水)に河出書房新社より発売されました。
今回お届けするのは、そんな木皿泉さんの「本屋さんの思い出」にまつわるエッセイです。お二人はともに大の読書家であり、ご自宅の蔵書量も相当なものだそう。そんなご夫婦ならではの、素敵なエピソードが綴られています。
 木皿 泉
木皿 泉
きざら・いずみ。夫婦脚本家。ドラマ「すいか」で第22回向田邦子賞、「Q10」「しあわせのカタチ~脚本家・木皿泉 創作の“世界”」で2年連続ギャラクシー賞優秀賞。ほかに「やっぱり猫が好き」「野ブタ。をプロデュース」「セクシーボイスアンドロボ」など。2013年『昨夜のカレー、明日のパン』で小説家デビュー。同作は本屋大賞2位、山本周五郎賞ノミネート。自身の脚本でドラマ化もされた。ほかの著書に『二度寝で番茶』『木皿食堂』などがある。新刊『さざなみのよる』は5年ぶり、著者2作目の小説。
- さざなみのよる
- 著者:木皿泉
- 発売日:2018年04月
- 発行所:河出書房新社
- 価格:1,540円(税込)
- ISBNコード:9784309025254
小国ナスミ、享年43。息をひきとった瞬間から、その死は湖に落ちた雫の波紋のように、家族や友人、知人へと広がっていく。命のまばゆいきらめきを描く、感動と祝福の物語。
(河出書房新社公式サイト『さざなみのよる』より)
「本屋さんの思い出」 木皿 泉
誕生日とかそんな特別の日ではなかった。私が買って欲しいとねだったわけでもない。何を思ったのか、母は私を市場の中にある小さな本屋の奥へ連れてゆき、好きな本を選べと言った。ときたま店先で主婦向けの雑誌を買うぐらいだった母も、そんな奥まで入ったのは初めてだったと思う。
本棚二つ分ぐらいの本が並んでいて、小学四年生の私は迷うことなく『耳なし芳一』を抜き取った。あまりのはやさに、母は「本当にこれでいいの?」と念を押し、私はうなずいた。母がネギやらイワシやらを買うたびに開く赤い財布から、私の本代を支払うのを見ていて、何だかとても不思議な気がした。私にとって、本は学校の図書館で借りるもので、期日までに読まねばならないものだった。あるいは、父や兄の本棚から、そっと盗むように読むものだった。
この本は、そんなのと違って、いつまでも堂々と手元に置いておけるのだ、と買ってから気づき、帰り道、やっぱり別のものにすれば良かったと悔やんだ。別のものとは、もっと華やかな、ふんわりとしたスカートをはいた人たちが出てくる西洋のお話とかである。
それでも、私は家に帰ると繰り返し何度も読んだ。私は本棚を持っていなかったので、その一冊は応接セットの椅子の隙間に差し込んだり、板間の床に読んだ形のまま放り出したり、ずいぶんひどい目にあわせたが、小泉八雲は何度読んでも飽きなかった。
怒涛のように本を読むようになったのは、会社員になってからで、その頃に自分用の本棚を買った。会社の帰り道に、大阪梅田の紀伊國屋書店と旭屋書店があった。当時、私は同じ仕事の繰り返しに渇ききっていた。獲物を持って帰らねばならぬ人のように、何かあるはずだと書店内を隅々まで歩き探した。
紀伊國屋書店は、阪急電車のホームの下にある広々とした店で、えんえんと続くお花畑でお花を摘んでいるような楽しさがあった。
旭屋書店はビルの中にあって、マッターホルンのそびえる山のように、本が上へ上へと積み上げられているイメージだった。だからなのか、ここに入ると、よし読んでやるぞという気持ちがふつふつと湧いてきた。当時、この書店には、どこに何があるのか熟知している書店員さんがいて、書名を言い終わらぬうちに、たちまちこちらが探している本を持って来てくれた。
こんなふうに大阪の本屋に入り浸っていたのは、まだダンナと会う前のことである。しかし、ダンナもまた、この時期よくこれらの店に出入りしていたらしく、私が話すと、あの店員さんはすごかったとか、人文科学の棚にどんな本があったとか、こと細かに覚えていて、一緒に行動したわけではないのに、それが二人の共通の思い出になっているのがおもしろい。
すでに旭屋書店はなくなり、紀伊國屋書店もあの頃の売り場とは、すっかりようすが変わってしまっている。なのに、私とダンナは三十年ほど前のことをまだ記憶していて、寝床に入ったときなど、そんな話をする。二人で一緒に、まだ出会っていなかった頃の書店の中を歩き回るのは楽しいことである。
私の本棚はいっぱいになり、初めて行った本屋さんの十倍ぐらいの本を持っていることに気づく。あの時の母のように、トマトやら挽き肉やらを買う財布で本を買い続けてきたわけである。
あの日、母は何を思って私に本を買ってくれたのだろう。繰り返される日常の中、OLだった時の私のように、母にも満たされない何かがあったのかもしれない。それを埋めるように、あの日ふと、子供の未来に向けて本を買ってくれたのではないか。
私自身、昔も今も本を買うことで、その場その場をしのいできた。そういう時、迷うことなく本棚から一冊を抜き取って買う私の癖は、今も小四の時のままである。
(「日販通信」2018年5月号「書店との出合い」より転載)