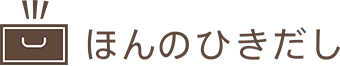書店にまつわる思い出やエピソードを綴っていただく連載「書店との出合い」。
今回は、山田風太郎賞受賞後第一作となる『臨床のスピカ』が8月23日(金)に発売された前川ほまれさんです。
前川さんは、看護師として働くかたわら、小説を書き続けています。動物介在療法がテーマの『臨床のスピカ』も、そんな前川さんならではの筆致で描かれた、DI犬という存在がさまざまな家族に寄り添う優しい物語です。
特に、作家になる前の若かりし日を支えたのが「本や書店の存在」だったという前川さん。今回は、前川さんが作家となったきっかけと、本や書店への思いについて綴っていただきました。
前川ほまれ
まえかわ・ほまれ。1986年生まれ、宮城県出身。看護師として働くかたわら、小説を書き始め、2017年『跡を消す 特殊清掃専門会社デッドモーニング』で、第7回ポプラ社小説新人賞を受賞しデビュー。2019年刊行『シークレット・ペイン 夜去医療刑務所・南病舎』は第22回大藪春彦賞の候補となる。2023年刊行『藍色時刻の君たちは』で第14回山田風太郎賞を受賞。その他の著書に『セゾン・サンカンシオン』がある。
だから、今日も
私の地元は、東北の海沿いにある。18歳の頃に夢を追って上京したが、数年で挫折してしまった。しかしその後、私は地元に戻らなかった。実家を威勢良く飛び出した手前、両親に合わす顔がなかったからだ。それに、誰にも会いたくなかった。友人からの連絡には応答せず、夢を諦めた自己嫌悪の暗闇に独りで沈んでいた。けれど生きている限り腹は減るし、生活費を稼ぐ必要がある。複数のアルバイトを掛け持ちし、なんとか暮らしていた。
アルバイト以外の時間は、自宅に籠って何冊も本を読んだ。特に、小説だった。今振り返ると、その世界に没入し、情けない現実から少しでも目を逸らしていたかったのだろう。
当時足繁く通っていたのは、近所の芳林堂書店だった。懐事情も踏まえ、購入するのは文庫本が多かった。目当ての作品を敢えて決めずに入店し、平積みされている小説や、書店員さんがお勧めしている作品に手を伸ばすのが常だった。新刊、古典、海外文学、ノンフィクション、タイトルだけは知っている名作。書店の静謐な空気を吸いながら本を選ぶ一時は、自らの情けなさや日常の閉塞感を忘れることができた。数々の本や書店の存在が、田舎者の挫折にソッと寄り添ってくれたのだ。
私はそれから一念発起し、25歳で看護師の免許を取得した。
看護師になって、2年目の夏。何かホラー小説を購入しようと、池袋のジュンク堂に向かった。その日は夜勤明けだったので、向かう道中から疲労で頭の中がぼんやりしていた。
店内のエスカレーターで目的階に到着すると、数々の小説が陳列する景色が目に飛び込んで来た。巨大ドミノのように並ぶ本棚、派手なポップが彩る話題書、平積みされた新刊、背表紙に書かれた無数のタイトル。何度も来たことがあったのに、私はその見知ったはずの光景に圧倒された。そして唐突に、ある想いが気泡のように湧き上がって弾けた。
「世の中には、こんなにも小説が存在してる。自分だって頑張れば、書けるかも」
夜勤明けで、判断能力が鈍っていたのだろう。浅薄な考えだと、今は思う。しかし「作家になりたい」と初めて強く願った。その初心を、今でもはっきり憶えている。
現在の私は沢山の幸運が重なり、看護師兼作家として活動できている。新刊『臨床のスピカ』を含めると、単著では5冊の小説を書いた。
刊行後の書店訪問では、書店員さんとお話しさせて頂く機会もある。面と向かって拙著の感想を頂く時は、嬉しさと恥ずかしさが交じり合い、少し頬が火照るのはデビュー時から変わらない。東北を舞台にした小説を書いた時は、地元の書店が大々的に応援してくれた。あの時の感謝や感動を、忘れることはないだろう。
私にとっての書店は、本を購入する場所だけではない。人生の節々で、かけがえのない時間を過ごした空間だ。時には、密かに背中を押してくれる場所でもある。
昨今、書店が閉店する知らせを目にすることが多い。その度、胸が痛い。誰かの救いや癒やしになり得る場所が消えていくのは、辛くて寂しい。たとえ、閉店する店舗に足を運んだことがなくても、私の中に確かに在る、書店で過ごした大切な記憶と重ねてしまう。足繁く通ったあのみずほ台の芳林堂書店も、今年の9月末に閉店するという。
作家として、今何ができるだろう。考えて、辿り着く答えはシンプルだ。心血を注いで魅力的な物語を生み出し、読者を楽しませる。そして、少しでも書店に貢献する。
だから私は今日も、小説を書いている。
著者の最新刊
- 臨床のスピカ
- 著者:前川ほまれ
- 発売日:2024年08月
- 発行所:UーNEXT
- 価格:1,980円(税込)
- ISBNコード:9784911106242
動物介在療法に携わるDI犬のスピカと、そのハンドラーの凪川遥が、横紋筋肉腫を患った5歳児、強迫性障害を抱える中学生、産後うつの患者や家族たちと向き合う。それは、凪川自身の内面にも変化を起こし、やがて大きな決断をすることに。動物介在療法を知るきっかけとなった同期との出会いとその後、育児放棄をした母とのこれから。犬と人との関係を通じ、人と人との心地よい距離と自分自身のありようを見つめ直していく。命の現場を舞台に、現役看護師の著者が描く希望の物語。
(U-NEXT公式サイト『臨床のスピカ』より)