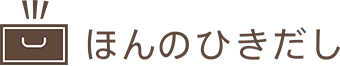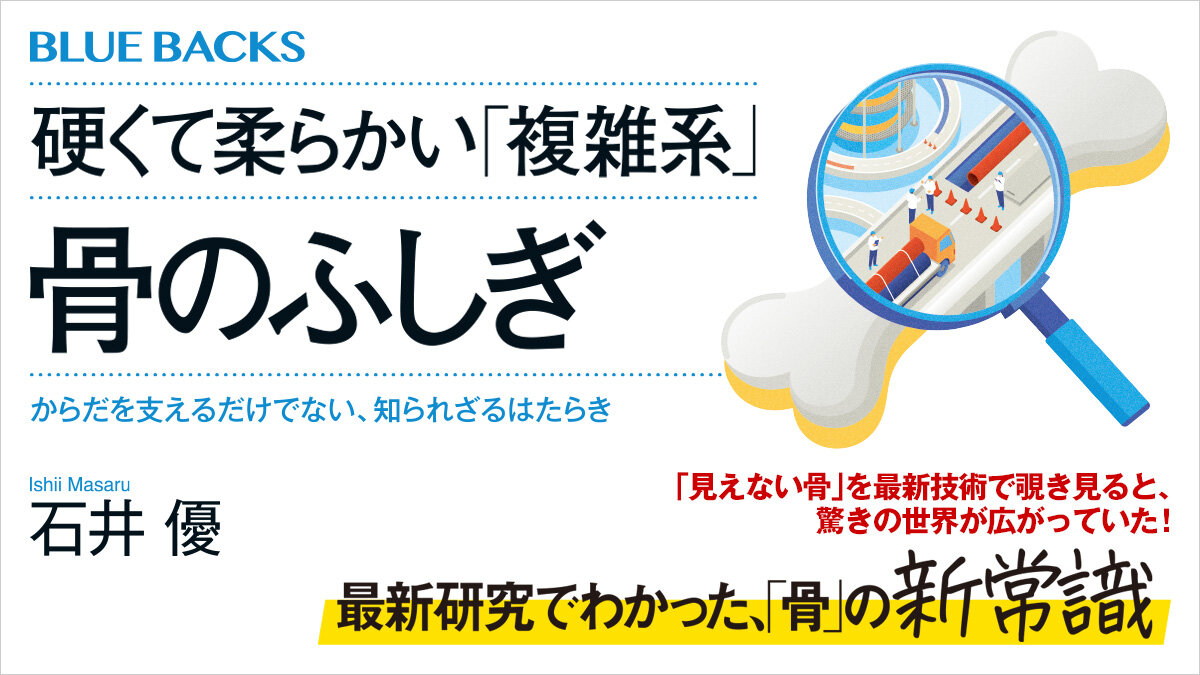柔らかく楽しめる「骨の本」
自分の手首をギュッと握って骨を感じてみたり、背骨や肋骨を指でなぞってみたくなる本だ。とても楽しい。
『硬くて柔らかい「複雑系」 骨のふしぎ』を読んでからというものの、隙あらば骨の話ばかりしている。フレンチで胸腺や雷鳥の頭蓋骨が出てきたら絶対に本書を思い出すはず。
骨は、生きているうちは皮膚に包まれて、多少のケガではまず見えなくて(見えたら大ケガだ)、カチコチで、ひたすら寡黙なパーツだと思ってきたが、実はとても雄弁で柔軟な存在だった。そしてダイナミックな働き者。
そうした骨の魅力がどんどん明かされる本だ。易しいところから少し難しいところまで、言葉の層が心地よく積み上がっていく。
たとえば、骨は「どんどんつくられて、どんどん消えていく」。
骨は歯と並んで身体の中で最も硬い組織の一つですが、実は、常に少しずつ壊されたりつくられたりしています。「壊される」と「つくられる」のバランスが保たれていることで、骨は一定の安定した状態に保たれているのです。これを動的平衡状態と言います。
「動的平衡状態」はこの本でたびたび語られる大切な言葉だ。骨の動的平衡状態とは次のようなことを指す。
壊される量とつくられる量が釣り合っていれば見かけ上は止まっているようですが、実際には動いているのです。
そう、骨はずっと動いている。そして壊される量とつくられる量のバランスが崩れると、骨粗しょう症などの病気につながることもイメージがつく。ちなみに、骨が少しずつ壊されてつくられているならば、ひょっとして子どもの頃の私の骨は、今はもうない?
計算上では、骨は約2~4年かけて全てが入れ替わることになります。
子ども時代どころか5年前の私を支えていた骨と今の骨は別! つい自分の足首の骨をニギニギしたくなる。でも、なぜそんな手間のかかることを骨はやっているのだろう……。
そんなこちらの疑問に著者の石井優先生はいろんな角度から答えをくれる。本書は「なぜ?」と思った次の瞬間には「なぜならね」と解説が始まる小気味よい本だ。
骨の動的平衡状態についての、ひとつめのシンプルな理由はこちら。
立ったり歩いたりといった、普通の生活をしているだけでも、骨には微小な「傷」が入ってしまい、放っておくと年月とともに積もり積もって、骨が脆くなって折れやすくなってしまいます。ですので、古く傷んだ骨を壊して、新しい骨をつくる、といった定期的な補修作業を常に繰り返しておく必要があります。これは高速道路の補修工事とよく似ています。
道路工事を見かけるたびに骨のことを考えそう。そして、なるほどなあ……と納得したところで「では“誰”が骨を壊して、つくるのか。そしてどうやって補修する場所を選ぶのか」という疑問がわく。そこで登場するのが、骨を壊す「破骨細胞」と新しい骨をつくる「骨芽細胞」だ。
生きたままの骨を見る
本書は、「見たことがない」ものが見えていく様子に胸が躍る本でもある。著者の石井先生は、生きたままの骨の中を見たことがある人だ。「二光子励起(れいき)顕微鏡」という顕微鏡を駆使して、生きたままの破骨細胞と骨芽細胞を見て、その動きを調べる生体イメージングに世界で初めて成功した。
破骨細胞や骨芽細胞などを蛍光標識することで、彼らの動きや働き方、また細胞同士のコミュニケーションなどが手に取るようにリアルタイムで観察することができます。(中略)これらの細胞間で交わされる“会話”の様子など、一見すると動きがないように見える硬い骨という組織の中では、細胞たちが忙しく動き回っていたのです。この体内の小さなプレイヤーたちの動きによって、健康で丈夫な骨がなりたち、私たちを支えているのです。
この破骨細胞と骨芽細胞のコミュニケーションの様子を捉えた写真が本書にも掲載されている。さらに本書内にあるQRコードを読み取ると動画を見ることもできて、破骨細胞と骨芽細胞がそれぞれブクブク動く様子がおもしろい。ふたつの細胞が明らかに協調して仕事をしていることがわかって、なかなか感動する。
破骨細胞と骨芽細胞の働きに加え、石井先生が生体イメージングを成功させるまでのエピソードや、そもそも二光子励起顕微鏡がどういう仕組みのもので、なぜ生体イメージングが重要であるかも語られる。研究者の仕事に触れる本としてもおすすめだ。
制御系としての骨、免疫・血液細胞を育てる骨
骨がどんどん壊され、つくられていく理由は他にもある。骨には、体を支える柱のような役目に加えて、大切な仕事がいくつもある。私が本書で一番興奮したのもこの点にある。
筆者は、この骨代謝の過程が、生体が本来備えている重要な調節作用点であることが挙げられると考えています。(中略)調節機構にとって重要なことは、簡単かつスピーディーに操作できることです。骨代謝は常に“創造と破壊”が繰り返されている動的平均状態にあるので、つくる側もしくは壊す側の速度を少し変えるだけで、調整が可能です。
本書の第4章では、リンやカルシウムといった生命活動に必要な無機イオンを貯蔵し、必要に応じて体内に放出する「全身の制御系」としての骨の仕事を学べる。骨は体をコントロールするホルモンも作っているのだ。忙しい!
さらに第5章では骨髄の中で起こっていることが解説される。骨の奥の骨髄では血液が作られているが、ではなぜ骨髄で作られているのか、どのように作られているのか(ここでも生体イメージングが大活躍する!)、そして骨と免疫システムの関係や、がんが骨にわざわざ転移し、困ったことを引き起こすのかが語られる。
個人的には、骨髄から旅立ったT細胞が胸腺で教育と選別を受ける話と、仕事を終えたT細胞やB細胞がやがて骨髄に戻ってくる話、そして骨髄にいる造血幹細胞が実は別のとある臓器から骨髄にやってきたという話がとても好きで、繰り返し読んでいる。直接見たことがないのに、骨のいきいきとした姿が目に浮かぶ。
ところで、石井先生によるコラムや「ちなみに……」といったこぼれ話も、本書の大きな魅力のひとつだ。骨という漢字のつくりに始まり、絵画や文学、そしてプラハの石畳からサン=サーンスの骨の音楽、果ては「骨と合うワイン」まで、骨にまつわる豊かで楽しい話題が飛び交う。どこを切ってもおもしろい本で、きっとお気に入りの骨エピソードが必ず見つかるだろう。そして骨のふしぎのとりこになるはず。ぜひ手に取っていただきたい。
*
(レビュアー:花森リド)
- 硬くて柔らかい「複雑系」骨のふしぎ からだを支えるだけでない、知られざるはたらき
- 著者:石井優
- 発売日:2025年05月
- 発行所:講談社
- 価格:1,100円(税込)
- ISBNコード:9784065398500
※本記事は、講談社|今日のおすすめ(書籍)に2025年6月19日に掲載されたものです。
※この記事の内容は掲載当時のものです。