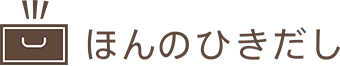『世界から猫が消えたなら』『四月になれば彼女は』『百花』などがベストセラー小説となった川村元気さん。前作『神曲』以来3年ぶりの小説作品となる『私の馬』が、9月19日(木)に発売されました。
実際に起きた多額の横領事件に着想を得た本作は、どのようにして生まれたのか。「馬との『言葉のない世界』にのめり込んでいく女性を、『言葉を信じて』描いていった」という川村さんへのインタビューをお届けします。
- 私の馬
- 著者:川村元気
- 発売日:2024年09月
- 発行所:新潮社
- 価格:1,870円(税込)
- ISBNコード:9784103542827
「ストラーダ、一緒に逃げよう」。共に駆けるだけで、目と目を合わせるだけで、私たちはわかり合える。造船所で働く事務員、瀬戸口優子は一頭の元競走馬と運命の出会いを果たす。情熱も金も、持てるすべてを「彼」に注ぎ込んだ優子が行きついた奈落とは? 言葉があふれる世界で、言葉のない愛を生きる。圧倒的長編小説!
(新潮社公式サイト『私の馬』より)

川村元気
かわむら・げんき。1979年横浜生まれ。上智大学文学部新聞学科卒。「告白」「悪人」「モテキ」「おおかみこどもの雨と雪」「君の名は。」「怪物」などの映画を製作。2011年に「藤本賞」を史上最年少で受賞。2012年、小説『世界から猫が消えたなら』を発表し、同作は32か国で翻訳出版された。著書に小説『億男』『四月になれば彼女は』『神曲』、対話集『仕事。』『理系。』、翻訳を手がけた『ぼく モグラ キツネ 馬』など。2022年、自身の小説を原作として、脚本・監督を務めた映画「百花」が公開。同作で第70回サン・セバスティアン国際映画祭「最優秀監督賞」を受賞。
10億円横領事件と通底する現代の生きづらさ
――本作は、一頭の馬に魅せられ、巨額の横領に手を染める女性が主人公の物語です。実在の事件がモチーフとなっているそうですね。
この3、4年、猫を飼い始めるひとり暮らしの友人が急に増えたのですが、その理由に、日常やスマートフォンの中の言葉にうんざりしているのではないかという思いがありました。僕自身もそう感じていた時に、10億円を横領してその大半を馬のために使ってしまったという女性のニュースを見たのです。突拍子もないニュースだけれど、僕らがいま抱えている生きづらさのようなものと、この女性の行動は通底しているのではないかと思いました。
そこで、日本全国の乗馬クラブを20か所ぐらい回り、馬にも130頭ぐらい会って、馬に対する理解を深めるところから始めました。
――作品を作られる際は、毎回100本以上のインタビューをされるそうですね。実際に馬と接せられる中で、どのような発見がありましたか?
本作の中に、『遠野物語』のオシラサマ伝説が出てきます。馬と結婚した女性の話として知られていますが、その伝説の地で、山に放たれている馬の手綱をただ引くというプログラムに参加しました。しかし、馬の体重は500キロありますから、力任せに引っ張っても動いてくれません。「行くよ」と言っても、当然言葉は通じませんから動かない。そういう時には待つしかなくて、馬と気持ちがシンクロした時に初めて動いてくれます。
いかに自分が日常で待つことができなくなっているか、言葉や力で相手をコントロールしようとしているかということを実感しました。
――主人公の優子は、偶然出会った一頭の馬に心を奪われ、人生を狂わせていきます。視線を交わし、無言のコミュニケーションを重ねることで、優子は「彼」にのめり込んでいきます。
小説でも書きましたけれど、馬に乗っていて感動したのは、右に曲がりたいなと思うと自分が動くより先に右に曲がってくれることです。人間の太ももの内側には太い血管があるので、馬は人間の意思や、興奮している、怖がっているといった感情もそこで感じるそうです。血流や体温、匂いといった、言葉ではない情報でのコミュニケーションは、人間が昨今失った感性だと思いました。
“脱線”とディテールが小説のおもしろさ
――そもそも優子は言葉によるコミュニケーションをとろうとはしない人物ですが、彼女についてはどのようにキャラクターを組み立てていかれたのですか?
今回は、実際にあった事件をモデルとしているのでかなり取材もしましたし、乗馬クラブを訪ねて、馬に乗っている方々がどうして馬に惹かれるのかということもインタビューしました。
寡黙な方が多かったのですが、コミュニケーションや誰かとわかり合えることを欲していないわけではない。だからこそ、馬とのコミュニケーションに快感を覚えるのではないでしょうか。それは僕も馬に乗っているときに感じたことですし、馬と触れ合っている人たちのディテールから見つけていったことです。
――馬は知能が高くで繊細であり、乗るとなれば命を預ける存在であればこそですね。川村さんの小説は、ストーリーだけでなく、積み重ねられたディテールによって人物像やその思いが重層的に伝わってきます。そういったディテールはどのように集められるのですか?
やはり取材ですね。100はサンプルを取らないと実際のところはわからないと思っています。
物語なのでフレームはある程度ありますが、その想定した枠組みから脱線していったときにおもしろいディテールが出てくるのは、小説ならでは。
馬が決められたコースから外れてしまったときに、どこへ行ってしまうのだろうと興味をかきたてられるのと同様で、小説は映画と違ってそれが許されるので、むしろ気持ちよく脱線するタイミングを狙っています。
たとえば今回で言うと、戌井というホストの男の子が出てきますが、彼は最初、登場人物としては存在していませんでした。優子と同じ乗馬クラブに御子柴という女性がいますが、僕自身が書いているうちに彼女を好きになっていって、優子と彼女を乗馬クラブではない場所で会わせてみたいなと思ったのです。ただ、あまり一対一で話すイメージがなかったので、御子柴が戌井という若いボーイフレンドを連れてくるという形になりました。
ちょうどそのころホストクラブに取材に行っていて、モデルになるようなおもしろいホストを見つけてしまったんです。まったくイケメンではなく、お話もおもしろくなかったのですが……、犬系男子というのか、一生懸命な愛おしいキャラクターだったので、作中のようなイメージのシーンになりました。

――動物とのコミュニケーションという側面があるからかもしれませんが、本作では血や匂い、音楽でもスキャットなど、自らの息遣いまで意識させられるような身体的な感覚が呼び起こされました。
言葉は一番理性に近い表現だと思うのですが、音楽、スキャット、相槌、鳴き声、暴力といったものもコミュニケーションのひとつだと思っています。私たちは普段そのことを忘れていて、全部を言葉で伝えないといけないという思い込みがあるけれど、馬について書いていると、コミュニケーションの多様性を感じました。
――本作でも、優子が突然暴力性を発揮する、印象的なシーンがあります。
暴力ってなかなか日常で振るわれることはないですよね。でも馬に乗っていると、僕も経験しましたが、理不尽に落とされたり蹴られたりしてびっくりします。馬は暴力を振るっているつもりではないけれど、人間にとっては脅威です。
馬に本格的に興味を持ったのも、山道で馬に乗っていたら、振り落とされて10メートルほど引きずられたことがきっかけでした。普段はそんなひどい目に遭わないので、逆に「すごいな、これ」と思ったのです。
――恐怖ではなく?
めちゃくちゃ怖かった。でも怖いとか傷つけられるといったことが、いまのコミュニケーションからは都合よくミュートされているのだなと再認識しました。馬には言葉がないから、噛むのもコミュニケーションです。そういったことからも、すべてを言葉で済まそうとすると何かを失うのだなと思いました。
――言葉ではなく、口角を上げることでコミュニケーションを終わらせようとする優子のクセも印象的です。
それもモデルがいるのですが、確かにニコッとしておけば話が済む側面はありますし、会釈も便利。本作では、自分が生きていて「こういうコミュニケーションは嫌だな」と感じることを、優子というキャラクターに仮託して描いているところがあります。
今回僕は、主人公に一言も喋らせないでどこまで書けるかをやってみたのですが、意外と人間って言葉がなくてもいけるな、やりくりできるのだなということがわかりました。
――そこは小説ならではの挑戦ですね。
映画では、主人公が2時間一言も喋らないという設定は難しい。そういう意味では、150ページという短めの小説だからできたことです。
他メディアでは体験できない“強度”が小説を書く理由
――本作では、登場人物それぞれに、人間の狡さのようなものがあぶりだされている気がしました。
たぶん、僕がこの小説を書いているときに、言葉はチートの道具だと思っていたからでしょう。楽してなるべく時短で済ませるとか、人を欺いたり、ごまかしたり、喧嘩したり、攻撃したり。スマートフォンの中にあふれている悪意や嘘、嫉妬や憎悪が日常世界を侵食しているイメージでした。
でもその人たちも一人ひとりをピックアップすると、別に悪意で生きているわけではなくて、自分の事情や守るべきものがある。優子の勤め先である造船所のシーンなどは、そういうネットの中のコミュニケーションを可視化したらこういう感じなのではないかと思って描いています。
――クライマックスに向かう中にも、優子が造船所で人々と対峙するシーンがありますが、読み手は優子の内面をすでに痛いほど受け取っているだけに、彼らに伝わらないもどかしさを強く感じました。
あのシーンはコミュニケーションのレイヤーそのもので、読者だけが優子とコミュニケーションができている瞬間です。現実では起こらないですが、物語ならではのマジックですよね。
あのすれ違いこそが今の現実の世界で起きていることなのではないかと思っていて、ある一室で起きている出来事が読み手にとっては悲劇で、優子をのぞく登場人物たちにとっては喜劇になっている。そんな、映画的な手法で書いています。
――映画化のご予定はあるのですか?
映画にしたいなと思っていますけれど、気づけば映画にできないシーンばかりになっていて、どうするのだろうと(笑)。例えば、リアルに国道を馬が爆走するシーンを撮ろうと思ったら大変ですが、その点、小説の乱暴さは最高ですよね。「国道に馬がいた」と一行書いて、「みなさん想像してくださいね」で始められますから。人間の想像力に依存しているメディアだからこそだと思います。
――映画製作や脚本でも活躍されていますが、そういった小説だからこその魅力を踏まえて、どのように執筆に向き合っていらっしゃるのですか。
僕は、小説は3年に1冊しか書けないので“自分が切実に知りたいこと”を書くようにしています。
今回知りたかったこととして、なぜ僕はこんなに言葉にうんざりしているのだろう、それなのに、なぜスマホや日常の言葉から逃げられないのだろうということがずっと頭にありました。小説を書くにあたって、その点はもちろん、動物と人間の関係性や横領事件やお金についても取材しました。そうすると、かなりの量の話を聞きますので、僕が知りたいことの“現在地”について知ることができます。その上で、それを物語化する過程で「なるほど、だからこうなんだ」「みんなはきっとこう思っているのではないか」という視点が立ち上がってくる。
『私の馬』は悲喜劇として書きました。ユーモアを交え、もしかしたらこちらの道のほうが幸福なのではないかと、みずからに問いかけながら書きました。取材で知り得た“現在地”よりももう少し先に行ける。そのゾーンに到達できるのは、1人で向き合う小説執筆の醍醐味です。
小説を読むという行為は、乗馬に似ていると思っています。読んでいる間はスマホを置いて、自分の記憶や感情と向き合う時間になります。他人の物語を読んでいるようで自分の隠された感情や苦しみ、悩み、喜びといったものを発見する時間が読書の強さであり、それはほかのメディアではなかなか体験し得ないのではないでしょうか。その強度がある以上、僕も小説を書き続けようと思っています。