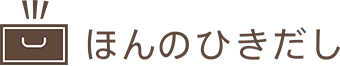©「隣の男はよく食べる」製作委員会
彼氏いない歴10年、気づけば35歳でさまざまなことに“曲がり角”を迎えた独身OL・大河内麻紀。その麻紀の前に現れたのがマンションの隣の部屋に住む年下男子の本宮蒼太。麻紀の手料理をたくさん食べる蒼太との恋愛を描いたラブコメ漫画『隣の男はよく食べる』(美波はるこ/集英社クリエイティブ)がテレビ東京でドラマ化され、4月12日(水)より放送されます(動画配信サービス「Paravi」では毎週水曜日21時より毎話独占配信中)。ドラマ化を手がけたのは「三匹のおっさん」から「復讐の未亡人」「にぶんのいち夫婦」まで幅広いジャンルのヒット作を世に送り出してきた山鹿達也プロデューサーです。どのような視点で漫画や小説作品をTVドラマにしているのか、山鹿氏にそのポイントを聞きました。

山鹿達也(やまが・たつや)氏
テレビ東京 制作局ドラマ室 チーフ・プロデューサー
群馬県出身。早稲田大学教育学部卒。1995年入社。制作局でドラマの助監督を経験し、番宣部などを経て、2003年より現職。プロデューサーとして「三匹のおっさん」シリーズ、「鈴木先生」「ハラスメントゲーム」「石川五右衛門」「アオイホノオ」「Iターン」「らせんの迷宮~DNA科学捜査~」「復讐の未亡人」などを担当。2018年より「ドラマParavi」のチーフ・プロデューサーを担当。
一緒にご飯を食べるという行為が今だからこそ大切
――今回、『隣の男はよく食べる』をドラマ化しようと思ったきっかけは何でしょうか?
実は、このドラマの脚本を執筆いただいた川﨑いづみさんからの推薦なんです。川﨑さんとはこれまでも一緒に仕事をさせていただいて、2022年1月クールの同じ枠で「部長と社畜の恋はもどかしい」という作品でも脚本を手がけていただきました。このドラマは若い女性と年上上司との恋愛でしたので、ちょうど地上波の放送が終了したときに「逆のパターンでやりませんか?」と相談したんです。そのとき、川﨑さんに紹介いただいたのがこの作品で、まさに望んでいた「年上女性と若い男性の恋愛」ものでした。
――実際に読まれて、どのような感想を持ちましたか?

©︎美波はるこ/集英社クリエイティブ
第一に、年の離れた男女2人が「お隣さん同士」という設定であること。次にその2人の恋愛をつないでいるのが「料理」であること。そして主人公の大河内麻紀が、「このままでいいのだろうか」と恋愛や人生を考える「35歳」という年齢だったこと。この3つの要素がそろったドラマはこれまでの恋愛ドラマにはなかった、と思いました。女性視聴者に刺さりそうな世界観だなと。
恋愛ドラマにおける男女の出会い方にはいろいろな形がありますが、自宅マンションの鍵を会社に忘れて、隣の若い男性の部屋にいきなり入っていってバルコニー越しに戻っていく35歳の女性というのは惹かれる存在ですよね(笑)。つまり、この出会いは2人が隣人同士でないと成立しないわけです。
――さらに、おっしゃるように、麻紀が手料理を蒼太にふるまう関係であることが特徴になっていますね。
その点で、このドラマは今のタイミングでやるべきという思いもありました。脚本家や監督たちと話したときに、コロナ禍で人と人とのコミュニケーションがどんどん減ってきたと言うんです。誰かと一緒にご飯を食べる機会もなくなってきたと。
食卓を囲めない。並んで食べる。しかも黙食。その中で、原作に描かれている「誰かのために料理を作る」「誰かと一緒に食べる」という行為は、シンプルなものなんだけれど、実はとても大事なことだったのではないかと思ったわけです。この春からコロナ禍での制約が取れてきて、少しずつそういう行為が自由にできるようになってきた今だからこそ、というわけです。
この作品の蒼太くんは、「いただきます」「美味しい」「ごちそうさま」という言葉をちゃんと口に出すんですよね。恋愛という枠だけにとどまらない、人と人とをつなぐコミュニケーションそのものの魅力がこの作品にはあるということですね。
――さらに、主人公は35歳の女性がいい、という狙いもあったと。
このドラマはネット配信のParaviで先行配信するので、もともと視聴ターゲットとしては20~30代の女性が中心だと思っています。特に35歳の壁と言われるように、大学を出て新卒から数えて一回り。もう若くもなく、とは言えまだベテランでもなく。
一方で、これまで実績をきちんと積んできた分、悩み始める年齢でもあります。恋愛一つとっても結婚や将来のこと、家族のこと、健康のことなど。ちょっとした曲がり角に差しかかった人のリアルな悩みや葛藤が描かれていて、そこに惹かれ、取り上げてみたいと思っていました。
スタッフのあるあるネタで、35歳女性のリアリティを追求!

――この作品をドラマ化するにあたって、とくに考慮されたことはありますか?
まだ連載中の作品ですので、2人の主人公のキャラクターを壊さず大事にしていくことは心がけました。細かい話ですが、たとえば蒼太が普段街を歩いているときは、ポケットに手を突っ込むかどうかまで議論しました。原作では、蒼太はポケットに手を入れていないんですよ。でも何かオリジナルエピソードを入れるときには、ちょっとカッコつけたがる蒼太を表現する意味で、その時だけポケットに手を入れるかどうか、議論しました。
さらに視聴者が、35歳の女性と25歳の男性の生活や恋愛の中に「リアリティ」を感じてもらえるように、台本打合せのときには川﨑さんや女性プロデューサーから、自身が35歳だったときの「あるあるネタ」を出してもらいました。たとえば、オープンカフェの席につくときにも、35歳を超えた女性は店内奥に行ってしまって、テラスや道路側の席には座りたがらないそうです。そういう要素も入れました。
――なるほど、キャスティングなどもそのあたりを配慮されたのでしょうか?
リアリティという点では、麻紀役の倉科カナさんもちょうど35歳なんです。彼女はすごく明るくサッパリしていて、麻紀のようにウジウジ悩んだりしないタイプですけれどね(笑)。蒼太役の菊池風磨さんと合わせて2人とも今までラブコメを演じてきたことがなく、初挑戦、初共演だったことも映像に初々しさをもたらしたと思います。
とくに菊池さんが割と人見知りするタイプだったので、2人が距離感を詰めていく感じが映像のほうにもにじみ出ています。蒼太という男性は、なかなか自分の気持ちをうまく言えない人なんですが、麻紀と一緒にご飯を食べながら接していくうちに段々成長していく。
ある意味、恋愛ものの王道なんですけれど、そのリアルさが出ているところが原作の魅力の一つでしょうし、菊池さんに演じていただくことでそこを表現できたと思っています。倉科さんは芝居にストイックで、遊び心を入れて自然体で演じていましたし、菊池さんは照れながらも食べ方や話し方を工夫しながら演じていました。
――原作のストーリーや設定で変えた部分もあったのでしょうか?

ドラマオリジナルの登場人物として、麻紀と蒼太に恋愛のライバルだけでなく仕事や生き方に影響を与えるキーマンの女性を作りました。市川由衣さんが演じる神野沙織という女性です。蒼太が以前アルバイトで働いていた会社の憧れの上司で、アメリカから帰国してデザイン会社を立ち上げるという設定です。
麻紀が選んできた生き方とは別の価値観を持った沙織という女性を登場させることで、麻紀は自分自身と蒼太とのことを見つめ直します。今は価値観が多様化して生き方もさまざまで、いろんな選択肢があるので、どれが良いか優劣を決めつけないようにしています。そうした選択肢から麻紀は何を選ぶのか?視聴者も一緒に考えながら見ていただけたらと思います。

――そのほか、映像化にあたり配慮されたところはありますか?
麻紀と蒼太の距離感ですね。隣同士でコミュニケーションを取り、さらに恋愛まで発展するのはオモシロイ。ただ至近距離で恋愛するのでケンカしたらリスクもあるし、その分、ドキドキが何倍にも膨らみます。お互いの存在を近くに感じるときもあれば、遠くに感じるときもあるわけです。その辺りの空気感は、監督の演出を含めて、気を使いながら撮影していただきました。バルコニーでの出会いからスタートしている恋愛ですので、バルコニーをその象徴として表現しています。心理的な距離が遠くなったときには2人が遠ざかっていることをバルコニーの撮り方で表現していますので、ぜひ見てください。ドラマのメイン監督は井樫彩さんで、そういう繊細な要素を綺麗に美しく拾い上げるのが得意な方です。
――普段から原作を探すために、小説などもよく読まれるのでしょうね。
小説やコミックは結構読みます。昔からサスペンスが好きで今も刑事ドラマも手がけていますから、ミステリーも読みます。先日も本屋大賞のノミネート作品などが気になりました。本屋にはよく行きますし、Amazonも見ています。
ただ、おもしろそうな本を手にとっても、読んでいるうちに「ドラマ化できない」と思うと、読むのをやめてしまうこともあります。
たとえばストーリーが荒唐無稽だったり、CGを使わないと映像化できない作品ですね。これは仕事目線でのこととはいえ、惜しいと思います(笑)。また今回のドラマのように、自分が忙しいときにはさすがに若い女性向けのライトな恋愛ものまでは手が回らないので、信頼できる方々から教えてもらうことも多いです。
ドラマの中に新しい「発見」がなければ今の視聴者は支持してくれない

――山鹿さんは多くのドラマを手がけて来られましたが、この作品に限らず、作品作りで常に心がけていらっしゃることはありますか?
今回のドラマは主人公の世代の女性たちがどう生きていくのか、そこを描きたかったわけです。物語の中で麻紀は恋愛だけではなく仕事や家族のこと、自分の将来についても悩みますので、その姿に共感してもらえたらうれしいですね。
「共感」が重要なのは、恋愛ドラマだけではなくサスペンスものや刑事ものも含めてどんなドラマでも言えることだと思います。やはりドラマとは人間を描くものですから。刑事ものだったらその刑事がどう犯人と向き合っていくのか、どう生きていくのかという姿に対して、視聴者が少しでも何かを感じてもらえることを大切にしようと思っています。実際ドラマの原作探しで小説を読むときは、物語の主人公がどう生きていくのか、それを見届けられる物語が作れるか、ということがポイントになりますね。
その物語に共感してもらうためには、やはりリアリティが必要だと思うんです。リアリティがあるからこそ、視聴者が共感できたり、何かを発見できたりする。視聴者にとってはこの「発見」が大切な体験になるわけです。
――ドラマを作っていくうえで、何か一つでも視聴者にとって「発見」できるところを作りたいということですね?

もちろん、ドラマは作り物である種のファンタジーですから、その中でどうやってリアリティを出していくか、そこが難しいところです。このドラマの設定のように「隣に蒼太のようなイケメンが都合よく住んでいることは現実世界ではまずない」でしょう。でも、いざそうなったときの2人のセリフにリアリティがあるので、視聴者は「もしかしたらこういうことが実際にあるかも」と思えてくるわけです。
そのためには、細部にこそリアリティを入れていくことが重要です。でもそこがムズカシイ。ストーリー展開や設定面では一緒にドラマを手がけている女性プロデューサーから「実際の女性はそうならない」「甘すぎる」といった指摘も受けました(笑)。
すでにドラマは最終回も撮り終えているのですが、2人の恋愛にはゴールがあります。自分としてはある程度ゴールの形は見えていたんですけれど、実際にどういうふうに着地させるのかを決めるときは、脚本家や女性プロデューサーとも侃々諤々やりました(笑)。結局、いろいろな生き方の選択肢がある中で、主人公の2人にはいろいろなことがあったけれどこれを選んだ、という感じの納得がいくゴールになっています。そこに、何かを発見してもらいたいです。
――たとえば、山鹿さんにとって視聴者に「発見」を提供したい素材はありますか?

今後ドラマで取り上げてみたいと思っているのは、たとえば郵便配達の人です。どこにでもいて存在を知らない人はいないと思うのですが、その暮らしやライフスタイルなどは詳しく知らない。ドラマや映画でもあまり取り上げられていません。普通に身近にいるのに詳しく知られていない存在に光を当てていくことで、何らかの「発見」につながると考えています。
逆に、これだけネットで情報があふれてドラマの数も増えている中では、既視感のあるドラマでは勝てないと思います。何か別の角度から眺めたり、何か斬新さがあったり、何か気づきや発見がないと、見てくれないんですよね。そうしないと埋もれてしまう。だから「発見」という要素は常に気にしています。
――その意味では、今後も斬新なドラマが生まれてきそうな予感がします。
直近では、世の中の不条理をテーマにした作品をやりたいと思っています。ドラマドキュメンタリーのような形ですね。会社から「やりすぎ」と止められる可能性はありますけれど(笑) 。
あと、夢なのか希望なのか、最後に前向きになれるような要素は入れて作りたいとは思っています。ドラマの最後は別にハッピーエンドである必要はないんですが、バッドエンドであってもその先に何か夢があったり希望があったりするドラマでありたいですね。
――ありがとうございました。