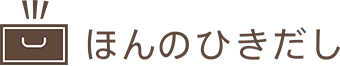4月4日(月)に発売された、早見和真さんの『八月の母』。愛媛県伊予市で起きた「少女暴行殺人事件」に端を発しながらも、著者独自の視点でその本質を読み解き、フィクションとして紡がれた長編小説です。
自身の代表作である『イノセント・デイズ』を、「今一度きちんと書いてみたい」という思いで再び描いた社会派作品。愛媛で暮らしたからこそ見えてきたものと本作に込めた思いについて、早見さんにお話を聞きました。
早見和真(はやみ・かずまさ)
1977年神奈川県生まれ。2008年『ひゃくはち』で作家デビュー。15年『イノセント・デイズ』で第68回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)、『ザ・ロイヤルファミリー』で2019年度JRA賞馬事文化賞と第33回山本周五郎賞を受賞。『店長がバカすぎて』で2020年本屋大賞9位。『あの夏の正解』で「2021年Yahoo!ニュース│本屋大賞ノンフィクション本大賞」ノミネート。他の著書に『スリーピング・ブッダ』『95(キュウゴー)』『ぼくたちの家族』『笑うマトリョーシカ』『かなしきデブ猫ちゃん』(かのうかりんとの共著)など。
- 八月の母
- 著者:早見和真
- 発売日:2022年04月
- 発行所:KADOKAWA
- 価格:1,980円(税込)
- ISBNコード:9784041109076
STORY
愛媛県伊予市。越智エリカは海に面したこの街から「いつか必ず出ていきたい」と願っていた。しかしその機会が訪れようとするたび、スナックを経営する母・美智子が目の前に立ち塞がった。そして、自らも予期せず最愛の娘を授かるが──。
うだるような暑さだった八月。あの日、あの団地の一室で何が起きたのか。執着、嫉妬、怒り、焦り……。人間の内に秘められた負の感情が一気にむき出しになっていく。強烈な愛と憎しみで結ばれた母と娘の長く狂おしい物語。ここにあるのは、かつて見たことのない絶望か、希望か──。〈KADOKAWA公式サイト『八月の母』より〉
浮かび上がった「仮説」と「母性」というキーワード
――2014年8月に伊予市の市営団地で起こった事件。早見さんは愛媛に引っ越して以来、ことあるごとにこの事件について尋ねられたそうですね。
僕が愛媛に引っ越したのは、その事件が起こった2年後の2016年でした。町の人たちにとってはまだ記憶が色褪せていない時期であり、僕が『イノセント・デイズ』を書いた作家だと知った何人かの方から「あの事件を知っている?」と聞かれました。僕は当時、事件そのものを知らなかったのですが、興味が湧いて調べたんです。しかしあまりにも凄惨で救いがなさ過ぎて、小説として何を書いていいのかわからない事件だなと思考が停止してしまいました。
愛媛には6年間だけ住むと最初から決めていて、3年ほど経ったころから愛媛に何を残していけるのかをずっと考えていました。1つは『かなしきデブ猫ちゃん』ではあったのですが、これだけではないなという気持ちがあって、もう一度この事件に立ち返りました。
3年前と同じように縮刷版や雑誌のコピーを読んでいると、読み味が微妙に変わり、ある仮説が立ち上がってきました。その仮説を関係者に当てて確認していくことが、今回の取材でした。
▼『かなしきデブ猫ちゃん』は「すべての愛媛県民の『ものがたり』を―。」との思いから書かれた創作童話
- かなしきデブ猫ちゃん
- 著者:早見和真 かのうかりん
- 発売日:2021年03月
- 発行所:集英社
- 価格:880円(税込)
- ISBNコード:9784087442199
――それが、タイトルにある「母」につながるのですね。具体的にはどのような仮説だったのですか。
「母性」というキーワードでくくっていいのかどうか、僕はまだ疑うべきだと思っているのですが、少なからず母性みたいなものが事件の根幹なのではないかというものでした。
つまり、加害者の女は事件を引き起こすために子どもたちを自宅に招き入れたのではなく、彼女自身が幼少の頃に求めていた、「母親の愛情」を等しく子どもたちに注ごうとした。それが僕の中に生まれた説で、加害者の過去を知る人たちに会って確認していきました。
「それは違う」という人が一人でもいたらそこで引き返そうと思いましたが、むしろその説を裏付けるようなエピソードがいくつも出てきました。もっと言えば、「やっとあの事件の構造が見えた気がする」という方もいて、それを聞いたときにこの小説を「書かなくては」と思えたのです。
――実際の事件は当時36歳の女が主犯とされ、その家に入り浸っていた複数の未成年によって引き起こされました。当時の記事を読み返してみても、目を覆いたくなるような内容のものばかりですが、なぜそこから母性というキーワードが出てきたのでしょうか?
具体的に何をとらえてそう思ったのかは定かではないですが、かなりの数の記事を見ていく中で、加害者の女は「すごく面倒見がよくて愛を感じた瞬間がある」といったコメントがありました。
実際の事件がどのようなものだったのか、被害者の少女がどういう家庭で育ち、なぜ現場となった団地に通っていたのか。僕が把握しているのは報道にあったレベルのことまでで、特別な取材はしていません。
なぜならモデル小説を書いたつもりはなく、仮説が証明された時点でまったく別次元の物語が立ち上がってきました。『八月の母』における団地の一室では何が起こり、加害者の女がどのような衝動で事件に関わり、殺された女の子はどういう気持ちでいたのか。それを物語っていったのが本作になります。
――モデル小説ではなくとも、センセーショナルな事件ではあったので記憶している方も多いと思います。そういった点で、執筆にあたって意識されたことはありますか?
『八月の母』が実際の事件に端を発しているのは事実ですし、モデル小説だと思われるかもしれないという覚悟はありました。舞台を伊予市にしないという考えもちらつきはしたのですが、あの事件を引き起こした要因の一つが地域性であることは、僕の中に確信としてあります。なので、そこは恐れずに書こうと思いました。
愛媛では自分から町に関わりにいったのですが、緩やかに守られ続けてきた土地で新しく何かを始めようとすると、こんなに苦しいのかと苛立ちを覚えましたし、衝突もしました。伊予市はその象徴的な町だと僕には捉えられたのです。
この物語はすべてエピローグに通じているという感覚が、書き始める前からありました。エンディングでは、本来はネガティブなものとして語られがちな「分断」とか「絆を断ち切る」というワードにこそ希望を託したかった。
それはまさに僕が『イノセント・デイズ』で書ききれなかったところだと思っているのですが、苦しいシーンを描き続けて、それがすべて反転するぐらいの鮮やかな希望をラストの伊予市の海に込めています。その海の見え方がエピローグで同じようにひっくり返れば、愛媛を救うことができるのではないかと思いました。
▼カバーにも伊予市の海の写真が使用されている
「男だからこそ書けた」母と娘の連鎖の物語
――プロローグは母になったばかりの女性の一人称で幕を開けます。この女性の正体はわからないまま、第一部では母親の呪縛から逃れられない、母娘3世代の人生が描かれていきます。この女性を主人公にしようということは、どの段階で思われたのでしょうか。
新聞や雑誌には書かれていない、もう一人の関係者の存在が、加害者を知る人の話から浮かび上がってきました。その真偽は定かではないですが、その話を聞いたときに、『八月の母』が誰を救わなくてはいけない物語かが見えてきたのです。その人物が、希望を、未来をつないでいくのだと思ったときに、この構造が浮かびました。
――中心人物となるのが、越智エリカです。
第一部は、男に首根っこを掴まれるエリカを書かなくてはいけませんでした。おそらく僕の今までの作品のなかで一番女を書く必要があり、そのためには男をきっちり書くことで女が浮かび上がってくる。保守性の強く残っている土地柄で、うんざりするような場面をたくさん見てきた僕が、自分自身を含めた男に対する刃を第一部で書いていった感覚が強くありました。
――男性である早見さんがそのような視点で男女を描くにあたり、もっとも苦労されたのはどのような点ですか?
何よりも、母と娘の物語を男である自分が書くことが怖かったです。そこを主戦場としている女性作家もたくさんいる中で、自分が書いていいのかという思いがありました。男に刃を向けて書く以上、古い、封建的な考えもあえて書いていますが、男が女を蹂躙しているシーンでは、それが僕の意見ととられてしまうのではないかという恐怖がずっと付きまといました。そこは女性作家であればおそらく恐れなくていい部分だったでしょうし、慎重になりましたね。
――ジェンダーについてさまざまな議論がなされるいまは、「母性」もデリケートなワードとなる場合がありますね。
愛媛で過ごして感じたのは、母性といったものが男も女も関係なく当たり前のものとして捉えられているし、誰も疑っていないということです。その中で、「自分は母親失格だ」と苦しんでいる母親たちにもたくさん出会いました。だからこそ、当然と思われているそれは、生きている人間が苦しんでまで守らなくてはいけないものかと、ジェンダー的な観点ではないところから書かなくてはいけない気持ちもありました。
エピローグでは、エリカの思いとは相反するセリフをヒロインに言わせていますが、これも男の僕が書くことで、すべてが台無しになるのではないかと不安がありました。それでも自分が想定していた以上のエンディングが書けたという手応えがあったことで、「男だからこの物語を書けた」というふうに思えたんです。
“自分を経由しない”視点で登場人物たちを見つめ続ける
――第二部は、紘子の視点で事件の核心が描かれていきます。さきほどお話のあった「殺された女の子はどういう気持ちでいたのか」をつぶさに追うことで、母性とは、愛とは何なのかを深く考えさせられました。
本作を書くにあたり『イノセント・デイズ』を意識したのは、作品の構造でも重さでもなく、「視点」でした。
- イノセント・デイズ
- 著者:早見和真
- 発売日:2017年03月
- 発行所:新潮社
- 価格:880円(税込)
- ISBNコード:9784101206912
『イノセント・デイズ』は一人の女性死刑囚の人生を、彼女の周辺にいる人物たちの視点で描いています。書き手である僕は透明人間となって、彼女の生まれたときから死刑の瞬間まで立ち会う。その「自分を経由しない」という視点を『八月の母』にも持ち込み、越智家3世代の女性を見つめ続けました。その上で、この物語の主人公はやはり紘子だったとも思っています。
本作を書くにあたり、実際の事件や被害者に囚われないことも、自分に課したことでした。被害者の家庭がどういうものなのか、彼女が何を思って死に至ったのか、被害者側の取材はあえて一切しなかったので、僕にはわかりません。ただ“紘子”をひたすら想像し、なぜ彼女があの団地に通い続けたのかを紐解いていくと、必然的に第二部の過程が立ち上がりました。
『八月の母』は「小説 野性時代」での連載を読んでくれている読者がすごく多かったのですが、特に紘子の家庭に対して思うことがある人は多かったようです。なかには、「母娘で僕の本を全部共有して読んできたけれど、この本は初めて読ませたくないと思った」という人もいました。娘との関係性に悩んでいる方で、僕から見ると全然そんなことはないのに置き換えて読まれていることが不思議だったし、普遍を描けたのかなと自信にもなりました。
僕にも妻と娘がいますが、僕は彼女たちの関係を俯瞰して見られるんですよね。娘が生まれてから2人を見続けてきたものがおそらくすべて込められているし、それは紘子の家庭の描写にも影響しているでしょう。
――紘子の家族という意味では、彼女の兄が終盤まで重要な役割を果たします。彼が「許すこと」について語る場面も印象的でした。
特に母と娘は、許す、許さないの関係なのではないでしょうか。そこをテーマにしようとは思っていなかったのですが、いま思えば確かにテーマの一つになっていきました。うまく言葉にできないですが、言葉にできないことの方が僕は本質だと思っています。
紘子の兄に関しては紘子の意図を汲んでの言葉であり、この本に出てくるすべての男の中で、僕は彼にもっとも希望を託しています。許す、許さないを口に出しているのは彼だけなので、そこには自然と僕の思いが入っているのかもしれません。
――簡単に言葉にできないからこそ物語として描かれているのだと思いますが、もう一つの重要なテーマが「自分の人生を生きること。人のせいにしないこと」ですね。これはずっと、早見さんが作品で書かれていることではないでしょうか。
確かに僕がずっと言い続けていることの一つですし、『八月の母』はそれを端的に書いた小説です。街から出ることを願いながらも、言い訳をし続けて流された人生の果てがエリカの姿だとするなら、エピローグで言い訳を拒絶した人間を描くことでその未来を指し示したかった。そういう意味でも、自分事として読んでもらえたらと思います。
――以前、「青春小説は作家としての“自分の背骨”」とおっしゃっていました。『イノセント・デイズ』『八月の母』といった社会派の作品は、ご自身の何に当たりますか?
「むかつき」ですね。世の中へのむかつきや腹立たしさを込めていますし、それはきれいごとではなく、自分に対する憤りでもあります。
結局は社会通念に縛られている自分に出会ったり、指摘されたり、男の優位性みたいなものを感じている自分を見つけてしまったり。そういう自分も含めて、僕が書く原動力としては、やはり「むかつき」が一番しっくりくるのではないでしょうか。
――社会派や青春小説だけでなく、コミカルなものから創作童話まで、さまざまなテイストの作品を発表されています。今後はどのように活動されていきますか?
2020年に『ザ・ロイヤルファミリー』で山本周五郎賞を受賞して、一区切りついた感がありました。手応えもあったし、結果もついてきましたし。
そのときに自分の胸に残ったのは、今の実力で『イノセント・デイズ』を書いてみたいということでした。100書こうと思って書き始めても、出来上がってみると、ずっと感覚的には5とか6しか書けていないんです。『イノセント・デイズ』もやはり10や20しか書けていないという感覚だった中で、『八月の母』を数値化したことはないですけれど、今回のエピローグは書けたという感覚が強かった。それは自分の成長と認めてもいいのではないかと初めて思えました。
小説に集中したいと籠りにいった伊豆で6年、開きにいった愛媛で6年、そして次の6年が東京で始まります。その6年の間に何を書くかというのは、おそらくどう生きるかと同義なので、悩みながらもその時々で必然性のあるものを書いていくだろうと思っています。その点は自分を信頼しているので、テーマとすべき切実なものに向き合っていきたいですね。
▼『かなしきデブ猫ちゃん』の愛媛3部作も完結!
- かなしきデブ猫ちゃん マルのラストダンス
- 著者:早見和真 かのうかりん
- 発売日:2022年03月
- 発行所:愛媛新聞社
- 価格:1,980円(税込)
- ISBNコード:9784860871628
- ザ・ロイヤルファミリー
- 著者:早見和真
- 発売日:2019年10月
- 発行所:新潮社
- 価格:2,200円(税込)
- ISBNコード:9784103361527
あわせて読みたい
・早見和真さんの伊豆の「創作の現場」を紹介!『イノセント・デイズ』刊行時のインタビュー