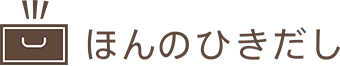『塞王の楯』で第166回直木賞を受賞した今村翔吾さん。2021年11月には、大阪府箕面市にある老舗書店「きのしたブックセンター」の経営を引き継いだことも大きな話題となりました。
フランチャイザーとして同店をサポートするのは、京都、滋賀を中心に書店を展開し、デビュー当時から今村さんを応援してきたふたば書房です。同社代表取締役の洞本昌哉さんと今村さんに、街の書店を残すことの意義と、今後の業界に望むことについて語っていただきました。
(2022年1月16日取材/「日販通信」2022年3月号【特集】「“街の本屋”はなぜ必要か? 3つの挑戦に見るその意義と役割」から一部抜粋・編集してお届けします)

▲(写真右から)作家・きのしたブックセンター 代表取締役 今村翔吾氏、ふたば書房 代表取締役 洞本昌哉氏。直木賞受賞後に行われたきのしたブックセンターでのサイン会に洞本氏が駆け付けた際のようす
作家が本屋を引き継いだ意味
――今村さんは、「本や書店に少しでも何か恩返しをしたい。業界に携わる者として、新たな書店の形を模索したい」と創業54年の書店を引き継がれ、昨年11月に新生「きのしたブックセンター」をオープンされました。オープンから2か月半を経て、現在のお気持ちをお聞かせください。
今村 まずは、やってよかったなと思っています。「きのしたブックセンターがなくなるのは困る」という声は、地域の方からかなりたくさんいただいていました。おそらく書店は身近にあって当たり前の存在で、なくなるかもしれないとなったときに初めてその大切さに気付くのではないでしょうか。そういうみなさんの気持ちを確かめられただけでも、引き継いだ意味はあったと思っています。
――洞本社長は今回の事業承継のお話をお聞きになって、どのように思われましたか。
洞本 正直、今村さんはお金が余ってんねやなと思いました(笑)。
僕は以前、銀行で行った講演会で、「こんな低金利で銀行に預けるぐらいなら、本屋をやった方がいいですよ」という話をして銀行に怒られたことがあります。「あなたがハッピーリタイアや定年で会社をお辞めになるとして、それまで30年なり40年なり働いてこられた中で培ってきた専門知識があるでしょう。世の中とのタッチポイントのひとつとして、その知識を活かしてニッチな本屋を経営するという考え方もありますよ」と。
今村 僕も本屋を始めて最初に思ったのは、これは僕でなくてもいいなということでした。もちろん洞本社長のように教えてくれる方がいればの話ですけれど、確かに初期費用さえどうにかなれば、いろいろな人がやれるだろうと。
いまリタイア後というお話がありましたが、働く期間が長期化している中で、自分のペースで楽しくできてやりがいもある、いいバランスでできる仕事なのではないでしょうか。
――きのしたブックセンターはふたば書房のFCとして運営されていますが、そのきっかけについて教えてください。
今村 僕がデビューしたのは2017年3月なのですが、まだ海の物とも山の物ともつかないときに、サイン会を開いてくださったのがふたば書房さんです。並んでくれたお客さんも15人くらいだったと思うのですが、その場で洞本社長が「この作家はこれから大きくなるから、今日のサインはすごくレアだよ」とおっしゃってくださって。
それから僕も何かあれば最優先でお応えしたいと思っていましたし、ラジオに出る際にお声掛けして来ていただくなど交流が続いていました。
洞本 我々のチェーンではずっと、各店舗で地元作家応援キャンペーンを行っています。そして、今村さんは弊社の滋賀県の店舗のお客様でもあります。もともとその店のスタッフが新しい作家を見つけるために、地元作家の本を読み漁っていて、今村翔吾という作家がおもしろいと思っていたそうです。そんなところに今村さんが来てくれて、「ご本人だ!」と大興奮で(笑)。
僕も読ませてもらっておもしろかったので、版元である祥伝社さんにお願いしてサイン会をやらせてもらいました。
▼きのしたブックセンターの店内のようす

店舗の運営には地域を知る人の存在が不可欠
――ちょうど今村さんのデビュー作(「羽州ぼろ鳶組」シリーズ)のお話が出たのでお聞きします。作家と作品を同一視するわけではないのですが、今回の書店を引き継いでほしいという思いに応え、地域に残すために尽力されているお姿は、作品とリンクするように感じています。
「羽州ぼろ鳶組」の主人公・源吾は、羽州新庄藩の壊滅した火消組織を再建してほしいと乞われ、仲間とともに組織を立て直し、自身も地域にとってなくてはならない人物となっていきますね。
今村 確かに作品と作家は別だという方もいると思いますし、僕自身も、もちろん100%イコールだとは思っていません。作家はいろいろな人間を創造して、描き分けなければならないので。
ただ、作品の根底に流れているものとして自分の魂的な部分を隠す必要はないと思いますし、作品にはそれぞれの作家の思いや生きざま、歴史などが乗っかってくるものでしょう。意識したことはないですが、「ぼろ鳶」の中に僕自身が込められている部分もあるでしょうし、今回の事業承継も根底の部分で似てくるのは必然かもしれません。
――直木賞受賞作である『塞王の楯』では、主人公の匡介は石垣職人の源斎に戦の中を助けられ、技術を受け継ぎながら、後継者となって組織を率いていきます。今村さんは、今回の事業承継で以前からいたスタッフの方とお店をつくっていくにあたり、どのようなことを一番意識されましたか。
今村 もっとも大切なのは、地域の人たちにいかに受け入れていただくかだと考えています。確かに僕が店を引き継いだことで、来店してくださるお客様もおられます。それはとてもありがたいのですが、割合としてはおそらく全体の5~10%ぐらいで、僕はそれで正解だと思っています。
ある意味、よそ者だということを自覚しながら入ってきましたので、そういう意味では「ぼろ鳶」の源吾と一緒かもしれません。「作家だからって偉そうに」と思われないように、腰は人一倍、低くしておかないかんなと(笑)。
洞本 今村さんの腰の低さはあきんど級ですから、そこは心配ないと思っていました。
先ほどの『塞王の楯』になぞらえれば、僕らが穴太衆(近江国穴太の石垣造りで知られる集団)となって、頭目をどのように支えていくかということでしょう。そのためにも、地域のスタッフがいてくれるのは何よりもありがたいです。
今村さんも初めから、従業員もそのまま引き継ぐという内容で契約されていましたので、僕はその点も共感をもってお手伝いさせていただこうと思いました。
街の“拠り所”、“交流の場”となるために
――今村さんは経営者として内側から書店を見るようになって、新たな発見や課題と捉えていらっしゃることはありますか。
今村 まだわからないことばかりですが、いいなと思ったのは先ほどもお話に出ていた再販制度ですね。僕は世間一般でいわれるほど悪いものとは思っていなくて、再販制度があるからこそ守られてきた部分も大きいと思います。ほかの商いにおいてはない制度ですし、返品ができるという点も、銀行の融資においてはプラスに働きますよね。不動産などと違って、価値が変動しないですから。
一方で、やり方とルールさえ守れば参入障壁は実は低いけれど、すごく高そうに見えていることが問題かなと思っています。
洞本 ちゃんと裏側を見ていますね(笑)。
再販制度に守られているから、資本の大きさでの勝負にはならないという考え方もあります。安売り合戦には巻き込まれない分、値段ではなくて、スタッフの人柄で勝負していく。
今村 いわゆるトータルな意味でのサービスが重要になってきますよね。
洞本 特に今回のコロナ禍においては、それを強く感じています。誰もが思うように外出できないなかで、本屋は幸いにして入るのも本をパラパラ見るのも無料ですからね。その中で「おはようさん」「こんにちは」とあいさつをして、お客さん同士も「今日は〇〇が安かったよ」とすれ違いざまに情報交換をしている。そんな、街の中で気軽に入れる空間を我々が維持しているわけです。
加えて知的な刺激を受けることで、「この機会にちょっと勉強してみようか」というきっかけにもなる。そういったことから、非常にたくさんのお客様に来ていただきました。
「毎日来て、何も買わんでごめんね」と言って帰らはるお客さんももちろんいますけれど、「うちは来てもらわないと商売になりません」とお答えしています。他人以上友達未満の、困ってはったら声をかけるくらいはできる関係で、毎朝店に行ったら誰かいるし、夜は遅くまで電気が点いている。そんな街の拠り所というか、灯台みたいな存在になれればいいなと思います。
――書店さんを街の交流の場にしたいということは、今村さんもおっしゃっていますね。
今村 洞本社長とまったく同じ思いです。こういったことについて、改めて詳しくお話ししたことはなかったですけれど、「わかってくれはるだろう」と真っ先に思いついたのが洞本社長でした。逆に、洞本社長を頼らないでほかの人にお願いしたら、「何で俺を一番に頼らないんだ」と絶対に怒られるなとも思いました(笑)。
洞本 もちろん、それは言いますね(笑)。
▼ふたば書房茨木店では、バレンタインデーからホワイトデーの期間に、店舗中央のシンボルツリーに大切な人へのメッセージを吊り下げてもらうお客様参加型の企画を実施。七夕は短冊、バレンタインはハート型のカードを用意
業界を救う一番の解決策は定価を上げること
――日販も出版取次として、街に書店様と本があり続ける世界を実現するため、出版流通改革に取り組んでいます。書店様マージンを30%にすることもその大きな柱の一つですが、粗利の問題についてはどのようにお考えですか。
今村 書店側から見れば、確かに粗利は少ないと思います。
作家の立場では、僕だけの問題ではないので、多くの作家たちの気持ちも含めて言うとすれば、「これだけの物語を書いたら、やはりこれぐらいの印税はいただきたい」という気持ちはあるでしょう。
両方を知っているからこその意見としては、本の定価を上げることが一番の解決策ではないでしょうか。映画の観覧料にしても、世の中の物価上昇に即して上がっていくのに対して、本だけが安いままのような気がします。
洞本 今村さんもおっしゃいましたけれど、映画を1本見るのも、文庫を1冊読むのも、同じくらいの時間がかかるはずです。ひょっとしたら文庫のほうが長くかかるかもしれない。どちらもエンターテインメントを楽しむ時間と考えれば、同じくらいの金額であっていいと思います。
インターネットがますます広がっていく中で、いろいろなコンテンツが出てきてライバルは増えているのだから、自分たちが磨きをかけて、いいものは自信をもって定価を上げていく必要があるでしょう。
また先ほどの再販制度の話に戻ると、唯一値段を決められるのは出版社です。売行きが鈍るというリスクを取ってでも上げざるを得ない社もあるでしょう。リスクを取る必要がなかったとしても、最近は無料の漫画サイトがありますよね。そこでたとえば3話までを無料で読めるようにすると、実際に店頭ではその続きから売れ始めます。
無料で種まきをしておもしろいと思ってもらえる作品には、読者を引き入れる魅力が絶対にあるはず。そこは読者とのタッチポイントとして、うまく活用してほしいですね。
今村 中途半端が一番良くないと思っていて、今後は無料と、特に趣味志向の強いものは高くても構わないという二極化になっていくと思います。無料のほうに寄ることはできないのだから、その良さを活用しつつも、自信をもって値段を上げていくしか方法はないのではないでしょうか。
――最後に、書店経営者としての今後の抱負をお聞かせください。
今村 僕が広告塔であることは、あくまでも一時的なフックでしかありません。繰り返しになりますが、地域のニーズをキャッチして、それを具現化して地域の人の生活の一部に組み込まれる本屋になる。箕面にはきのしたブックセンターだよねと言ってもらえるように、決して油断することなく1年目より2年目、2年目より3年目という形で進化できるように取り組んでいきたいです。
こんなケースはめったにないからこそ、プラスの業績を出したいなと。数字が悪かったとしても、次に何をしようとしているかといったことまで公にしていきたい。
これまでとまったく同じ形ではなくても、本屋には可能性と未来があることを示す突破口の一つになれればと思います。『童の神』という作品では、道あるところを進むのではなく、道なきところに道を生む苦労を知る、そんな生き方を主人公たちに託しました。僕自身もそれを実践していきたいです。
洞本 今村さんは、やはり作家さんならではの表現力をお持ちだなと感じています。本屋にはまだ多くの魅力が眠っているにもかかわらず、我々がうまく表現できていなかった部分もあるでしょう。こうやって表現のプロが書店業に入ってくださったのだから、本屋の魅力を大いに広めていただきたい。少しでもそれに気づいてくれる人が増えれば必ず本の世界はまた盛り上がってくるでしょうし、本にはそれだけの力があると思っています。
今回、作家である今村さんが、書店を引き継ぐというアクションを取ってくださったのはすごく大きいことです。地域には、業界の内外を問わず、その知識や能力を書店業で発揮してもらえる方がきっといるはずです。その人たちとのマッチングを進めることも、本屋を活性化する一つの方法ではないでしょうか。そうやって、いろいろな地域で文化の明かりを灯し続けられたらいいですね。
今村翔吾さんは、2月15日発売の『イクサガミ 天』(講談社文庫)を皮切りに、5作品の連続刊行が決定しています。それを記念し、「本屋さんを応援したい」という今村さんの思いを受けた「今村翔吾 書店へ5・5キャンペーン」が実施中。くわしくはこちらをご覧ください。
※本対談のロングバージョンを掲載した「日販通信」2022年3月号の情報はこちら