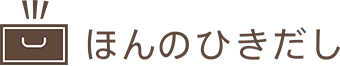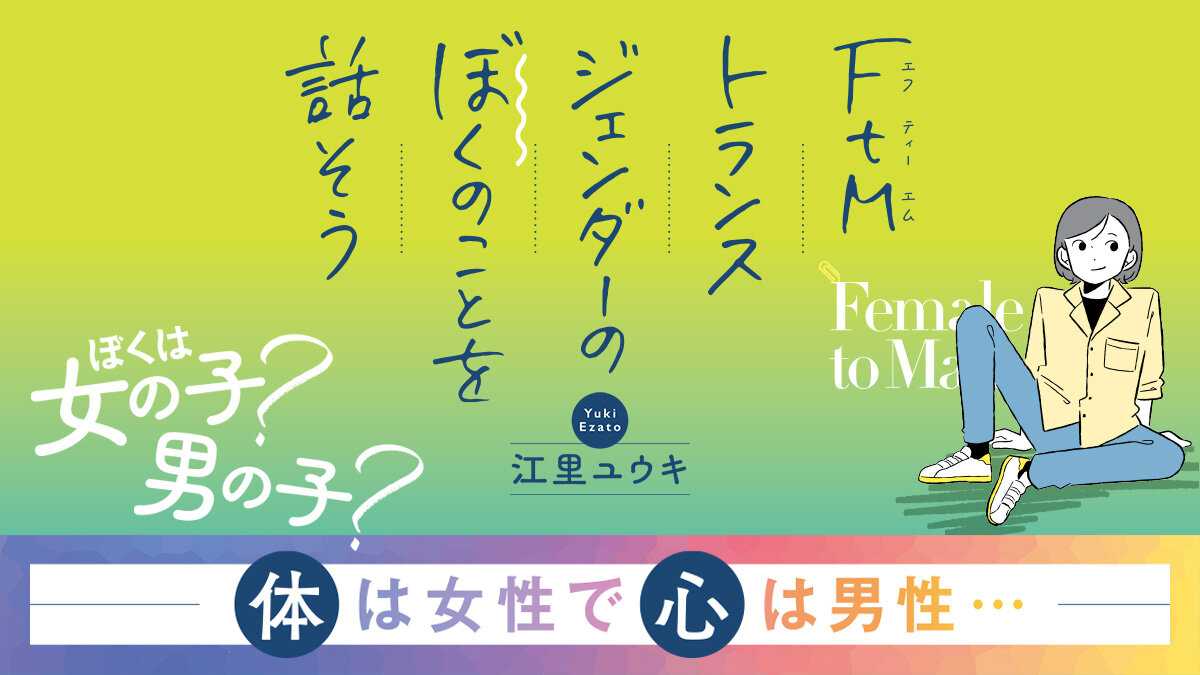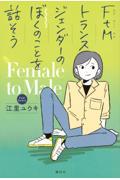ぼくは昔から“普通(ふつう)”というものに憧(あこが)れて生きてきて、普通になりたかったし、普通に生きたかった。
そう語る著者は、身体は女性で心が男性の「FtMトランスジェンダー」として生きる20代の若者。読者のなかには「それって普通じゃなくない?」と思ってしまう人もいるかもしれない。でも、人それぞれに「普通」のかたちはある、ということを本書はハッキリと教えてくれる。
著者はこの本で、波乱万丈と言って差し支えない自らの体験を率直に綴る。そして、今まさに同じような問題に直面している少年少女、あるいはトランスジェンダーへの理解を深めたいと思っている読者に対して、つとめてやさしく平易な言葉で語りかける。本書の対象年齢が「小学上級・中学から」となっているのも、できるだけ早く若い読者の助けになれるように、という願いからだろう。
漢字にはルビがふられ、専門用語もわかりやすく解説されるので、幅広い層に安心して読んでいただきたい。もちろん、先述のように狭いイメージの「普通」に囚われてしまっている人々も含まれる。
トランスジェンダーとは何か。そこにはどんな悩みがあるのか。そして「それ以外の人」が何をわかっていないのか。そういった基本的な疑問も、この本は明らかにしていく。読者は多くの知識や発見をここから得られるのではないだろうか。
今も男性器がほしいとは思っていないし、つけたいとも思わない。
こういうところは個人差(こじんさ)が大きいのだと思う。
体を手術(しゅじゅつ)してでも完全に反対の性になりたい人もいれば、そこまで求めていない人もいて、自分は何者なのか、ということにも、本来の性にどれだけ近づきたいかにも、グラデーションがある。
だからそういうところは十把一絡(じっぱひとから)げにして、あなたたちはこうなんでしょう? と決めつけてほしくないと思う。
大事なのは本人がどう感じ、どうしたいと思うか、なんだから。
著者が自身の性別について初めて違和感を覚えたのは5歳のときだったそうだが、明確にトランスジェンダーとしての性自認を得たのは、だいぶ後になってからだった。そのぶん、混乱や戸惑い、痛切な苦悩の時期は長かったという。本書の対象年齢が若めに設定されているのも、本人の「長く険しい道のり」の実感からだろう。
ぼくはいわゆる“男の子が好きそうなもの”が好きなタイプの男の子ではなかったから、余計(よけい)にわかりにくくなったのだと思う。ヒーローにも電車にもまったく興味(きょうみ)がなかったのだから。
だから自分も、親やまわりの大人も違和感(いわかん)を持たなかったのだ。
当時の自分の気持ちを思い出すと、自分でも自分のやってることがよくわかってなくて、それでも変だと思われない範囲(はんい)で、精(せい)いっぱい男の子をしていたような気がする。
趣味やタイプの問題かと思っていた些細な違和感も、成長していくにつれ、「生きづらさ」となって膨らんでいく。著者にとっては決して遠い昔ではない思春期の描写は、痛切そのものだ。あのころ感じた真剣な絶望、大人になるまでの途方もない時間の長さも、本書はまざまざと思い出させてくれる。その感覚はきっと普遍的なものでもある。
登校時間になってもぼくが部屋から出てこないので、見に来た母に「学校に行きたくない。」と何度も繰(く)り返(かえ)した。
父もやってきて、どうしたんだと聞かれたけど、「学校に行きたくない。」としか言えなかった。自分の気持ちや状態(じょうたい)を説明できなかった。
どうして行きたくないのかを尋(たず)ねられ続けたのだが、自分でもよくわからないものを答えられるわけがない。どうにか言えたのが「精神科(せいしんか)に行きたい。」というセリフだった。
生々しい当時の述懐のなかには、衝撃的な告白も含まれる。おそらく、リアルタイムで似たような状況にある読者もいることだろう。そういうときに「自分だけじゃないんだ」という感覚を得ることは、何かの救いになるかもしれない。
“ちゃんとした女の子”になれば、ちゃんと大人になれる……。
ちゃんと大人になって、ちゃんと仕事について、ちゃんと子どもを産んで、ちゃんと、ちゃんと……。
自分がなんなのかわかりかけたことで逆に混乱し、中三のとき精神(せいしん)が不安定になった。
そして十五歳(さい)のとき、自殺未遂(じさつみすい)を起こした。きっかけは本当にささいなことだった。
というか、きっかけはなかったと言ってもいい。
高校進学後、著者はついに性自認の瞬間を迎える。人生全体からすれば、決して遅すぎるタイミングではないようにも思えるが、苦しみぬいた本人にとってはとてつもなく画期的な出来事であったことが、読者には鮮烈に伝わってくる。それは人間にとって、自分が何者であるかを知ることがいかに大切か、という真理を痛感させる場面である。
この出来事を通して、“自分は性同一性障害(せいどういつせいしょうがい)かもしれない”と口に出したことで、今まで持っていた数々の疑念(ぎねん)が確信(かくしん)に変わりはじめたのだ。
心のなかでぼんやり思っているだけなら、なんとか押(お)し殺(ころ)すことができていたけど、一度音にして外に出してしまうと、なんというか、固体になった、「性同一性障害」という文字にガンと殴(なぐ)られたようだった。
するとその途端(とたん)、今までの大小さまざまな違和感(いわかん)が一気に襲(おそ)いかかってきた。
(中略)
こういうことの全部が全部、自分は女の子じゃないから、女の子になりたくなかったからだ、ということに気づいたのだ。
言葉には力があり、それによって人は前に進むこともできる。そんな効能も本書は教えてくれる。以降、著者が解放されていく過程、懸命に「生きること」に食らいついていく姿は、羨ましいほどに感動的だ。年齢や人生経験を問わず、そういう大切な「自己発見」を果たしている人が、今の社会にどれだけいるだろうか、とも考えてしまう。
ここで、ぼくは体の性は女で、性自認は男、性的指向は男性だとわかって自分を明確(めいかく)に定義(ていぎ)できるようになり、とてもすっきりした。
それがハッキリしたことで今までの「体は女で男性(だんせい)が好きだけど、男として男性を好きになるから同性愛者になるってなんなんだ!」という頭のなかがこんがらがる謎(なぞ)みたいなものが解決した。
トランスと同性愛は両立するのだ!
(中略)
ぼくは男として男性に愛されたい。それがおかしいことではないとわかって嬉(うれ)しかった。
セクシュアルマイノリティとしての自我を獲得した著者だが、それで完全に悩みから解放されたわけではない。新たな困難や挫折も経験し、体の違和感を取り除くための大きな決断もすることになる。だが、彼は紛れもなく自ら道を切り拓く強さを得て、「普通に生きる」という目標に向かって突き進んでいく。
普通について、生きやすい状態(じょうたい)について、長い間自分なりにいろいろ考えた結果ベストな状態が今のぼくだからこれでいい。
人にはそれぞれベストな状態があると思う。
そのままがいい人、見た目だけ変えられればいい人、いらないものをなくしたい人。いろんな人がいて、みんなそれでいい。そう思えるようになった。
まだまだ無知や偏見にさらされているトランスジェンダーの生き方について、この本は多くの理解を読者に与えるだろう。同時に、現代における多様性とその受容について、極めて普遍的なメッセージを投げかける1冊でもある。その先に見据えるのは、誰もが「普通に生きられる」社会だ。
*
(レビュアー:岡本敦史)
- FtMトランスジェンダーのぼくのことを話そう
- 著者:江里ユウキ
- 発売日:2025年04月
- 発行所:講談社
- 価格:1,650円(税込)
- ISBNコード:9784065390641
※本記事は、講談社|今日のおすすめ(書籍)に2025年5月15日に掲載されたものです。
※この記事の内容は掲載当時のものです。