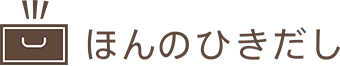2013年に『スターティング・オーヴァー』で作家デビューし、若い世代を中心に根強い人気を誇る作家・三秋縋さん。特に、デビュー2作目である『三日間の幸福』は60刷30万部を突破、『恋する寄生虫』は2021年に実写映画化され、2018年には『君の話』が第40回吉川英治文学新人賞にノミネートされるなど大きな話題となりました。
人間関係や内面的な葛藤が繊細な文章で表現され、SF的な設定も取り入れられた独自の世界観が多くの読者を虜にしている三秋さん。そんな持ち味がふんだんに盛り込まれた6年ぶりとなる青春ミステリー『さくらのまち』が発売されました。
本作はどのようにして生まれたのか。また、三秋さんが小説を書く上で大切にしていることはどんなことなのか。三秋さんにメールインタビューでお答えいただきました。

『さくらのまち』
著者:三秋縋
発売日:2024年9月26日
発行所:実業之日本社
定価:1,980円(税込)
ISBN:9784408538662
二度と戻らないつもりでいた桜の町に彼を引き戻したのは、一本の電話だった。
「高砂澄香が自殺しました」
澄香――それは彼の青春を彩る少女の名で、彼の心を欺いた少女の名で、彼の故郷を桜の町に変えてしまった少女の名だ。
澄香の死を確かめるべく桜の町に舞い戻った彼は、かつての澄香と瓜二つの分身と出会う。
あの頃と同じことが繰り返されようとしている、と彼は思う。
ただしあの頃と異なるのは、彼が欺く側で、彼女が欺かれる側だということだ。人の「本当」が見えなくなった現代の、痛く、悲しい罪を描く、圧巻の青春ミステリー!
(実業之日本社公式サイト『さくらのまち』より)
三秋縋さん プロフィール
みあき・すがる。1990年、岩手県生まれ。2013年、『スターティング・オーヴァー』でデビュー。繊細で透明感のある文体が、若者から圧倒的な支持を得る。『君の話』で吉川英治文学新人賞にノミネート。おもな著作に『三日間の幸福』『いたいのいたいの、とんでゆけ』『君が電話をかけていた場所』『僕が電話をかけていた場所』『恋する寄生虫』など。
登場人物は自身の分身のような存在
――まずは、どのようなきっかけから本作が誕生したのかについて教えてください。また、本作では「自殺ハイリスク者」に寄り添い、自殺を阻止する「プロンプター」と呼ばれる“サクラ”が重要な存在となっています。そういった舞台設定はどのように生まれたのでしょうか?
前作『君の話』を書き上げた後、何を書いても途中で投げ出してしまうような時期が続きました。以前だったら問題なく完成まで持っていけたであろうプロットも、「これを書いたところで前作の縮小再生版にしかならないな」と感じるようになったんです。
そんな中、車に乗って気分転換にあちこちを走っていたら、「ところざわサクラタウン」の看板を見かけました。その文字列を見て、反射的に「住人全員がサクラの町」を連想したんです。誰もがこちらに好意を持ってくれるけれど、それはマッチングアプリのサクラみたいなものに過ぎない。虚しい嘘に塗れた世界と「さくらのまち」という言葉の響き、この二つが頭の中で組み合わさったとき、「これなら最後まで書き切れるだろうな」と心のどこかで確信している自分がいました。
プロンプターまわりの設定は、既存の自殺予防システムが歪な発展を遂げたらどうなるだろうという想像のもとに生まれました。SNSに投稿されたテキストから自殺の兆候を検知して通報するようなシステムは実のところ既にいくつも存在していて、その仕組みがそう遠くない未来に実現されるであろう高度な監視社会に最悪の形で組み込まれたとしたら、おそらくこんな風になるのではないかと。
自殺対策というのはその性質上いくら工夫したところでどこかしら歪で不自然で矛盾をはらんだものになってしまうジレンマがあるんですが、その歪さをあえて誇張したことで、人間の猜疑心というものを描く上で効果的な舞台になったように思います。
――本作を描くにあたって、主人公の尾上やヒロインの澄香、その妹である霞、物語のカギを握る鯨井といった人物は、どのように設定されたのでしょうか。それぞれ人物造形のヒントとなったものはありますか?
いずれの人物も特にモデルになったような人物などはおらず、ある意味では僕の分身のような存在です。「他者が描けていない」という定番の批評がありますが、僕はそもそも一人の人間が自分以外の他者を描くことなんてできないと思っているんです。
他者と自分とのあいだに重なり合う部分を見つけて、そこを描き出すことはできます。でも根本的に思考システムの異なる人間を描くというのは、極端な話、猫の気持ちになって書けというのと同じくらい無茶な話です。仮に描ける部分があるとしたら、それは人間の思考と少なからず重なり合う部分だけです。一方で、一人の人間には様々な側面があり、中には真正面から対立しているような要素も少なからずあります。
そうした対立を取り上げて作中の人物に仮託して対話させることには、「猫の気持ち」と自身を対話させることよりよほど意味があるように思うんです。
――三秋さんの作品では、「町」というものが舞台として大切に描かれていると感じます。本作では特に雪の情景が印象的ですが、岩手出身である三秋さんの原風景とつながるところもありますか?
僕が生まれ育った土地は関東の基準からすれば一年の半分が冬のような気候だったので、自分にとってもっともしっくりくる空間を描こうとすると、自然とそれに近いものになります。寒くて薄暗くて透き通った匂いがして、吐く息は白く、靴底には雪がまとわりついている。僕にとってはそれが当たり前の感覚だったのですが、関東に移り住んでからというもの、そういう感覚とはほとんど無縁になりました。
当時は一刻も早く春が来ることばかり待ち望んでいましたが、今になって記憶の中から心地良い風景を取り出そうとすると、地元の冬の風景ばかりが思い浮かぶんですよね。
「人間として生きることって、そんなに悪くない」と思える美しさ
――本作では〈システム〉や〈手錠〉などですが、作品にはしばしばSF的なギミックが登場します。そういった仕掛けを施される狙いについてお聞かせください。
僕たちの住む世界とよく似た世界ではあるけれど、小さな何かが決定的に異なる世界である、ということを示す際に、その差異をただ文字で説明するのではなく、手に取って触れられる具体的な何かとして示した方が、読者にとって直感的に「違う世界」が理解しやすいんですよね。その「小さな何か」を示す上で適切なサイズの異物が、本作では〈手錠〉にあたります。
――本作からは、翻訳小説のような、またハードボイルドのような雰囲気を感じる読者もいるのではないでしょうか? 文体で意識されたことはありますか?
意識的に文体的な努力をしたことはないんですが、自分の小説にとって一番効果的な文体を無意識に選び取っているという感覚はあります。僕は感傷的な物語が好きなんですが、そうした感傷を描く際には感傷的な文体は逆効果になるんです。ジョークはできるだけ真顔で言うべき、本人が笑ってしまうと効果が半減してしまう、というのは誰にでも理解できる話だと思うのですが、それは感傷にしても同じなんです。感傷的なことはできるだけ素っ気なく言うべきなんですね。
――死を扱った作品を多く書かれていますが、作品における死の位置づけについて教えてください。
これは決して僕の作品に限った話ではなく、物語というのは現実以上に死に溢れた世界ですよね。平均一人は確実に死んでいる。それは死というものが現実においては絶対的に取り返しの付かない事象であり、かつ相対的に生というものを浮き彫りにする重要な事象であるからこそ、物語という形で摂取しておきたいと人々が願っていることの反映ではないでしょうか。
――「虚構」や「嘘」、同時に「本当」や「真実」なども三秋作品に共通するキーワードかと思います。小説家である三秋さんにとって、虚構とは、また小説とはどのようなものかお聞かせください。
僕にとって物語とは、真実ではないけれど、真実と仮定してもなんら不都合のない嘘、真実と仮定することで生きやすくなる嘘、とでも言うべきでしょうか。僕は作品の中で、状況の在り方に嘘をつかせることはあっても、人間というものの在り方に嘘をつかせたことはないつもりです。少なくとも人間についていえば、「起きても不思議ではないこと」が起きるようにしている。
本作で言えば、サクラを生み出すシステムは嘘だけれど、サクラに対する人々の反応は極力本物に近づけようとしているわけです。そうした物語の中で、何かしら美しいものが生まれたとしたら、その美しさは現実の人間にも適用することができる。その結果、「へえ、人間として生きることって、そんなに悪くないじゃん」と思えるんです。
作家と読者のちょうどいい距離感とは
――「読みたいやつを書きました」とXでコメントされていますが、今回一番「読みたかった」と思われるポイントはどこですか?
特定の場面が描きたかったということではなく、一行一行、僕にとって心地よい文章になるように心がけたという意味での発言ですね。場面と場面の繋ぎになるなんでもないような文章でも、そこにずっと留まっていたくなるような、その箇所だけ取り出してもなんらかの機能を保つような、そういう文章になるように心がけました。
――これまでの作品の中でもっとも長く執筆にかけられたとのことですが、具体的にはどのくらいの期間がかかっているのでしょうか? また完成までにとくに苦労された点、執筆中の印象深いエピソードなどをお聞かせください。
本作が出るまでに前作から6年ほどの空白がありましたが、実際に本作に費やした時間はせいぜいが2年というところだったと記憶しています。
「さくらのまち」というアイディアを得てからは特に苦労した記憶もありません。結局、作家の一番の仕事って、書くことそのものではなく、書くに値する何かを見つけることの方だと思うんです。そして一人の人間にとって書くに値するものって、そんなに多くは用意されていません。書けば書くほど、切実なテーマはどんどん消費されていきます。
だから本作に限った話ではありませんが、僕が一番苦労している仕事は、「さくらのまち」の看板と出会うために車を走らせるような、そういうたぐいのものです。
――6年ぶりの書き下ろしということで、待ちわびていた読者も多いと思います。読者へのメッセージがありましたら教えてください。
僕個人の考えを言えば、作家と読者というのは互いに存在を強く意識しながらも目は合わせないくらいの距離感がちょうどよいので、直接的なメッセージというほどのものはないのですが、これだけ安価な娯楽にあふれた世の中で、本を買って読んでいただけるというのは本当にありがたいことです。僕の独りよがりな楽しみが、たとえ偶然にでも読者の方々の心のどこかを震わせてくれることを願っています。