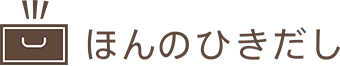作家デビュー10年を経た塩田武士さんの新作『朱色の化身』は、60年以上前に福井県で起きた大火を題材に、昭和、平成、令和の時代を通じて、失踪した女性ゲームプランナーという架空の人物の人生を、リアリズム小説という手法で鮮明に浮かび上がらせた社会派大作です。
わずかな資料をもとにその時代の当事者に取材を重ねて得たのは、ネットにも書籍にも残されていない事実と、自らの仮説を覆す現実。スマホ検索で知りたい情報が簡単に入手できると考えられがちな現代で、私たちはその虚実にいかに向き合うか。塩田さんはリアリズムを追求した小説こそが、その思考の一助になると語ります。『朱色の化身』ができるまでを伺いました。
- 朱色の化身
- 著者:塩田武士
- 発売日:2022年03月
- 発行所:講談社
- 価格:1,925円(税込)
- ISBNコード:9784065249994
【内容紹介】
「知りたい」――それは罪なのか。
昭和・平成・令和を駆け抜ける。80万部突破『罪の声』を超える圧巻のリアリズム小説。「聞きたい、彼女の声を」 「知られてはいけない、あの罪を」
ライターの大路亨は、ガンを患う元新聞記者の父から辻珠緒という女性に会えないかと依頼を受ける。一世を風靡したゲームの開発者として知られた珠緒だったが、突如姿を消していた。珠緒の元夫や大学の学友、銀行時代の同僚等を通じて取材を重ねる亨は、彼女の人生に昭和31年に起きた福井の大火が大きな影響を及ぼしていることに気づく。作家デビュー10年を経た著者が、「実在」する情報をもとに丹念に紡いだ社会派ミステリーの到達点。
(講談社BOOK倶楽部より)
“実”の中に“虚”を浮かび上がらせ人間と社会を描く
――読後に再度読み直すと、何気ない一文が伏線になっていて、その度ごとに発見があります。
情報量が尋常ではないので何回読んでも何かしらの発見があります。アニメ業界について書いた『デルタの羊』(2020年刊)では業界事情などを深く取材しました。今回の『朱色の化身』はたった1人の人間を表すために、最初からテーマをもって話を聞きにいくのではない、いわば「曲線的」な取材をしました。
中心人物の辻珠緒は元銀行員の設定です。銀行関係者への取材では、1986年の男女雇用機会均等法の施行以降の女性行員の働き方や、使っていた表計算ソフト、女性の社員寮のことまで細かく聞きました。
作品の舞台となる福井県あわら市の取材では、大きな題材の1つである芦原大火のときに脱走したシェパードが町中をうろついていたことなど、書籍や当時の新聞などには文字情報としてほとんど残っていない話を聞くことができました。
こうした、実際に起こったことで周囲を固めて、その真ん中に虚である辻珠緒という人物を浮かび上がらせました。ある架空の個人を描きながら、その人物が生きた時代、社会を描くという手法で、この小説に出てくる登場人物以外の“情報”は大半が実在します。
リアリズム小説には3つの型!「キーワード」をたどる取材
ーー本作の着想はどこから生まれましたか。
まずは創作方法についてお話しさせてください。
グリコ森永事件を題材にした『罪の声』を一緒に作った編集者さんが、「リアル・フィクション」という言葉を作ってくれました。まず、この意味を言語化しないといけないと思いました。
そこで『朱色の化身』を書く前に、1つの論考をまとめようと思いました。そのために、「実在」「再創造」「細部」「リアリズム」「姿勢」「取材」「虚実」「時間」の8項目に分けて、自分が書きたい小説を3、4か月かけて分解していきました。何を書くかではなく、
それで見えてきたのが、リアリズム小説には3つの型があるということです。
1つ目は『罪の声』の「トレース型」。モデルの事件・人物をそのままトレースして成り立つ小説です。膨大な事実と同じだけの闇がある。その事件の歯車を細かく組み合わせていくと小説になるという型です。
2つ目は髙村薫さんの傑作『レディー・ジョーカー』のように、その事件から本質を抽出する「モデル型」。
そして『朱色の化身』は3つ目の型である「キーワード型」です。モデルはないけれども、自分の興味のあるキーワードを取材して共通項を見つけていく。たった1人の女性を浮かび上がらせるためにキーワードを設定して、何も分からない状態で進めていくような手法です。ある意味、すごく怖いことをしたくなったんです。
取材で覆される仮説が、登場人物の造形に生かされた
今回は、そのキーワードを「ジェンダー」「テクノロジー」「報道」の3つに絞りました。
僕はジャーナリズムとメディアの視点を持ち続けていれば、医療小説、警察小説と同じように「報道小説」がジャンルとして確立できると思っています。記者は実際に社会のいろいろなところに出ていくことができるので、どこに放り込んでも違和感がありません。そこから「マス」と「個」の関係を突き詰めて考えていきました。
ジェンダーも「#MeToo」運動があったように、2017年以降の世界で大事なキーワードです。ネットでは「つかみ」というか、見出しの立ちやすいものばかりが拡散されている。本質はそこではなく、単純に不公平であることを指摘しないといけません。
テクノロジーについて、僕は大きなテーマとして社会のあり方を含めて「虚実」を常に考えています。フェイクニュースが典型ですね。
最近だと、ネット上で仮想のなりたい自分に「アバター」でなれます。取材の前には、「自分が作り上げたアカウントやアバターに依存することがすでに起きていてもおかしくない」と仮説を立てていましたが、ネット依存研究で著名な先生に聞くと「今のところ、そういう患者は1人もいない」との答えでした。
取材前の仮説が覆されて、現実の方に寄っていく。ラグビーボールのように、どこに転がっていくか分からないんですよ。これらの取材で得た事実が、登場人物の造形に深く生かされています。
わずか2行の史実に注目!芦原での取材が物語の大きな柱に
ーー序章「湯の街炎上」は昭和31(1956)年に福井県あわら市で起きた芦原大火の描写から始まります。この舞台設定にどのような過程でいきついたのですか。
編集者に福井に行こうと誘われ、目的地の前に地元電鉄の一番端の駅まで行くことになりました。そしてたどり着いたのが、日本海に面した三国港でした。元々、日本海側の夕焼けから夜にかかる感じの小説を書きたいと思っていましたが、その雰囲気に合致しました。
その後、福井でロケハンしたときに、タクシーの運転手に「雄島に行ったことがありますか」と聞かれました。地図を見てみるとRPGのラスボスが出てきそうな地形で、雄島と本島には220メートルにもおよぶ橋がかかっていました。これを見た瞬間に「書きたい」と。この場所と、あわら温泉街をつなぐ構想が浮かび上がってきました。
▲取材で訪れた物語の舞台となる「雄島」と本島を結ぶ橋
いまは営業していませんが、町で一番栄えた旅館「開花亭」の前の神社には、芦原の歴史について、たったの2行で「昭和31年の芦原大火で温泉街は灰塵に帰した」と書かれていました。
簡潔に書いてありますが、「2行で終わる話なのか」と取材を始めました。フェーン現象で温泉街が大火に見舞われましたが、直接亡くなった方はいません。そのせいか、地元の方々に取材しても、詳細に覚えている人がほとんどいませんでした。記憶の風化も怖いと思いました。
しかし、当時の住宅地図を片手にいろんな角度から聞いていくと、曖昧だった記憶のなかからさまざまな事実がわかってきました。火事場泥棒があった場所、暴力団が運営していたブルーフィルムの映画館や、その近くでお色気写真が販売されていたことなど、当時の記憶の細部が浮かび上がってきました。この芦原での取材が物語の大きな柱になりました。
▲大湊神社で新作の取材をする塩田さん
2割の事実を徐々に「裏切る」リアリティ
ーー序章に続いて、第1章が事実、第2章が真実となります。失踪したゲームプランナー・辻珠緒をライターの大路亨が探します。大路が後半で「真実は事実の解釈だ」と思い至るように、事実がどんどん覆されていきます。
僕は新聞記者でしたので、紙面になるのは2割だけで、あとの8割は書けないことを体験的に知っています。その2割の部分の辻珠緒をまず書く。世に出やすい情報を事実パートに配置し、次の取材パートで辻珠緒の違う面、つまり残りの8割が出てくる。この「裏切り方」もミステリー小説のようにわかりやすい裏切り方ではなく、グラデーションがあって徐々に気持ち悪く変化していく。これがリアリティなのではないかと。
取材でたくさんの人に話を聞いて、いかに自分の仮説が浅いかを実感しました。珠緒はヒットコンテンツを送り出したゲームプランナーですので、専門学校に行く設定にしました。しかし、実際にはそういうケースはほとんどないようです。それよりも、取材したゲームプランナーさんが丸3年の製作期間をかけて黙々と「サウンドノベルゲーム」をつくったと聞くと、その孤独感のほうがよほど人間的で面白い。それも珠緒の造形や過去に生きています。
こういう事実はグーグルでは得られず、人に話を聞かないと出てきません。大路の気づきは作者である僕の気づきでもあります。
ーー後半に珠緒と母、咲子の間で雄島であった出来事の真実が明かされます。この重要なシーンで読者がページを開いた瞬間に思わず息を呑むような文章上の仕掛けもありますね。
それは偶然なんです(笑)。簡易製本のプルーフと単行本で同じページ組みができるかわからないのですが、もし同じだとしたらこの小説はなかなかの運を持っていますね。ただ、作中のいたるところで当初からそういう裏切り方をしようと意図はしていました。これは僕が好きで読み続けている松本清張の短編によくあるのですが、大きなオチよりも細かく突き放すと言いますか。書くほうからすると、なかなかしんどい作業ではありますが(笑)。
マスメディア、個人双方にある「驕り」
――大路は父から個人的な頼みとして辻珠緒を探すことを引き受けたのに、いつの間にかそれ以上のことに変わっていきます。この過程でジャーナリズムが求める「公の利益」と「個」が向き合うことについて思いをめぐらします。そこでは「驕り」という言葉も使っています。
これまでは新聞、テレビが大きな存在でした。新聞は記者クラブ制度、再販売価格維持制度、個別宅配制度の3つの仕組みに支えられています。
記者クラブによる官公庁に張り巡らされた取材網。再販制度で小売り価格が維持され、個別配達によって安定的に宅配ができます。新聞という“問屋”がいなければ情報が届きませんでした。放送は免許制ですし、電波は限られています。つまりマスに頼らざるを得ませんでした。
▲オンラインインタビューで質問に答える塩田さん
いまでは、これまでマスメディアが担っていたことが、SNSで個人や少人数でできるようになってきました。無論、信憑性の問題は残っています。
公のメディアからすると「載せるに値しない」という取捨選択をしないと成り立たない。裁判官のように情報を裁いていくんです。これは構造的に驕りを生みます。マスメディアは自らの驕り体質を反省しなければならない。
一方で、個人も自分で伝えたいことを編集し発信できる。それによってマスコミを否定することで、自らの正当性を主張するスタイルにも危険性があるのではないか。
結局、事実が大事であることを私たちが共有することが第一義。ネットを見るとセンセーショナルなもの、面白いものは拡散する。まさにポスト・トゥルースです。現状我々は、事実に対していかに向き合うか、受け入れるかの基本的な心構えができていません。
小説で書いたのは、事実を突き詰めるために人に話を聞き、資料にあたること。マスと個が冷静になって事実に向き合うのが健全な姿だと思いますが、まだ道のりは遠いようです。
SNSについては、発信側が賢くなるしかない。そういう意味を含めて報道小説が必要ではないかと。リアリティと娯楽性をかなり高い次元で融合させること。これが自分が書きたい小説の基本にあります。そのためには作家である自分が足で稼ぐこと。検索しても出てこないことがこの小説にはいっぱい入っている。それだけで価値があると信じています。これが活字・小説の強さです。
直面する被害者の悲哀と加害者の後悔
――終章「朱色の化身」は、これまで錯綜してきた数多くの事実から真実が明かされます。とくにラストシーンが鮮烈な印象を残しますね。
最初に雄島に訪れた時に、ここで雪を降らせて結末を、と決めていました。逆算していうと、冒頭の芦原大火の火事場泥棒の現場で何があったのか。そこで起こったことは偶然でも、その一家や人物の人生に深く関わっている。大路はその人が人生の中で長く、重く抱えてきたことに直面します。被害者の悲哀、加害者の後悔は当事者にしか分からないものがある。双方の間に余計な情報が入っていないだけ面と向かって向き合えるのではないかということを書きたかった。
タイトルにもある『朱色の化身』は珠緒が中学生のときに読んだ句の一節。これは僕のオリジナルですが、その意味について、ぜひ想像していただきたいです。読み終えた方がそのタイトルをどう解釈するか。その楽しみは読者に委ねたいです。
――刊行に先駆けてこの小説ができるまでのドキュメンタリー映像も製作されました。
私から編集者に提案しました。長尺、中尺、短尺の3本あります。テーマは「説得力」です。これだけ取材をして事実に迫っているんだから、面白くないわけがないだろうという説得力です。「小説はフィクション」と思う人がいますが、実から虚をつくる意義を映像でも残したかったんです。
最初の映像の冒頭は3年前、この小説の原形がまったくないところからカメラに入ってもらいました。『騙し絵の牙』でも映画化になる前から主人公に俳優・大泉洋さんをあてがきして書きましたが、メディアの中の小説とはどういうものなのかを常に考えています。
▲講談社BOOK倶楽部HPで公開している『朱色の化身』特別ドキュメンタリー(取材編)
ーー2022年でデビューして11年目になります。これからどんな作品を書いていきますか。
42歳になりましたが、国防、憲法、資本主義……といった社会の中心にあるものに対して挑戦していく年齢になっています。おそらく3年後くらいから取り掛かるでしょうが、その時も自分の実力からすれば背伸びして書くことになるでしょう。不安はありますが、新しいことに取り組む不安をいだく方が健全かなと。自分が挑戦したいと望んでいることの方が実は一番大切です。
小説はすごく深くて、なくてはならないものだと思っています。リアリティと娯楽性を高い次元で両立させつつ、人間と社会を描いていきたいですね。世の中にいろいろなエンタメがあふれて、いま小説は不利だと言われます。しかし私は、唯一無二になりつつあると捉えています。活字こそ一番情報を圧縮できる。本を読み終えた後の充実感、情報量に、かなうものはありません。
▲講談社BOOK倶楽部HPで公開している特別インタビュー
▲同HPで『朱色の化身』プロモーションビデオも公開中