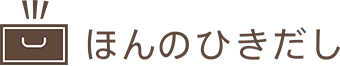本書は、「サイバネティクス」と呼ばれる科学の、とくにその知られざる後期についての書である。
冒頭に書かれたこの言葉通り、著者は本書において、サイバネティクスという学問の誕生から、それが内包していたもう一つの思想とその理論を、全7章を通じ解き明かしていく。
著者によれば、そもそも「サイバネティクス」とは、
生物と機械を統一的な観点から理解しようと構想された、分野横断的な科学の名である。米国の数学者ノーバート・ウィーナーによって一九四八年に提唱されたが、彼が単独で生み出した学問というよりも、専門領域を異にするさまざまな学者が参画した、一種の知的ムーブメントであったといった方が正確である。
サイバネティクスは、精神とコンピュータ、より一般化して言えば、生物と機械を同一視する思想として、今日まで広く受容されてきた。
そうだ。「機械は人間になり、人間は機械になる?」と題された第1章では、映画『マトリックス』や『攻殻機動隊』、『ブレードランナー』を例にとりながら、サイバネティクスが現実へ溶け込んでいくことで、人間・生物機械論である「コンピューティング・パラダイム」というものの見方が成立してきた過程を語る。
続く第2章では、「コンピューティング・パラダイム」と相反する思想である「サイバネティック・パラダイム」が論じられる。後者は人間・生物非機械論であり、本書の主題でもある。いずれも「サイバネティクス」を元にしており、対極なパラダイムがどうして同じ起源から生まれたのか、その経緯は興味深い。
1980年生まれの著者は東京薬科大学生命科学部環境生命科学科を卒業後、同大学大学院生命科学研究科で修士課程を修了した。その後、東京大学大学院学際情報学府修士課程を経て、同大学院博士課程を単位取得退学。情報学を専門とし、現在は東海大学講師を務めている。
ところで私が本書を読もうと思ったきっかけは、第4章「オートポイエーシスの衝撃」にある。かつて、学生時代に取った「科学哲学論」の講義の中で、私はこの思想を学んでいた。
当時の担当教授にはいくつもの逸話があった。たとえばそれは、「講義中に喋っていた学生を注意したところ、学生は教室を退出した。すると教授は大学から徒歩15分の最寄り駅まで、その子を追いかけ走っていった(その間、他の学生は教室に残された)」とか「講義中に教室へ豚を連れてきた(なぜかは忘れた)」、「前方に座った学生にあだなをつけて毎回名指しする」など、一風変わったエピソードばかり。入学したての身にその真偽のほどは不明だったものの、興味を持った私は教授の専門領域である「オートポイエーシス」なる概念にも触れたくなった。
結果として、教授の講義は面白かった。だが内容は予想以上に難解で、当時の私は語られる内容を書き留めることだけで精一杯。その思想が理解できたとはとても思えないまま、一年を終えてしまった。だからいつか機会があったら、少しでも学ぶことができたらと願っていた。
すると思いがけず、本書がその機会を与えてくれた。1973年にチリの生物学者であるウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラによって提唱された「オートポイエーシス」の概念を、マトゥラーナが1960年にチリ大学医学部生物学科に着任したところまで時間を巻き戻し、そこから丁寧に紐説いている。ちなみに「オートポイエーシス」という言葉はマトゥラーナとヴァレラによる造語で、
「オート」は自己、「ポイエーシス」は産出や創造を意味するギリシア語で、この二つをつなぎ合わせた
ものであり、生命という一つのシステムがどのように組織化されているのかを指している。なおその詳細は、第4章をじっくりと読み込んでほしい。いまだ生半可な私がお伝えするより、著者の念入りな解説をそのままお読みいただいた方が、難解な内容も頭にするっと入るに違いない。
オートポイエーシスにより補完されたサイバネティック・パラダイムは、時を経て、新しいサイバネティクス「ネオ・サイバネティクス」へとたどり着いた。最終章の第7章で、著者は本書全体を振り返りながら、現在注目を集めるAIに対する視点や分析にも触れている。専門的かつ硬派な1冊であり、興味のある方には恰好の教科書と言える本書。すべてを理解できたとは言えない私も、少しずつ読み直すことで知り続けたい。
*
(レビュアー:田中香織)
- 人間非機械論 サイバネティクスが開く未来
- 著者:西田洋平
- 発売日:2023年06月
- 発行所:講談社
- 価格:2,255円(税込)
- ISBNコード:9784065317785
※本記事は、講談社BOOK倶楽部に2023年7月11日に掲載されたものです。
※この記事の内容は掲載当時のものです。