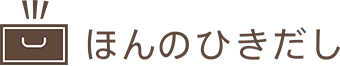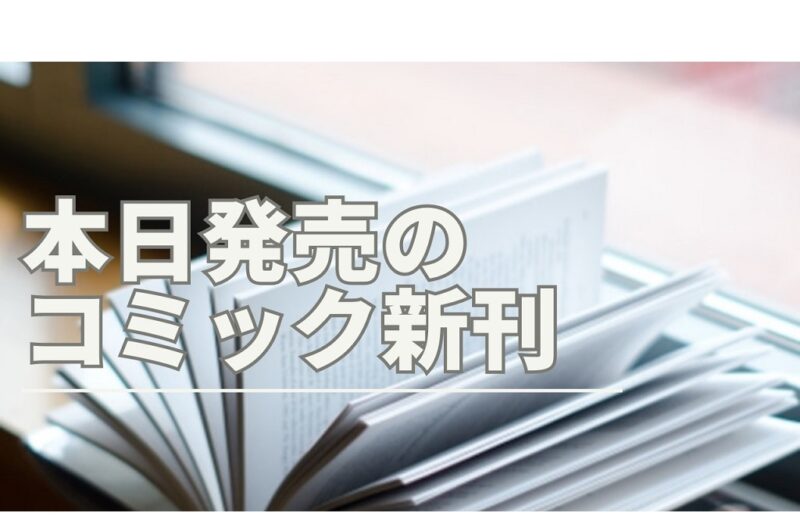2023年12月13日(水)発売のコミック単行本をお知らせします。
イースト・プレス
・ノス&ザクロ(ラリアット)
・アフターメルヘン(上)(田島生野)
講談社
講談社コミックス別冊フレンド
・たまらないのは恋なのか(1)(空華みあ)
・ごめんね初恋(2)(帆那みつき)
BE LOVE KC
・ハグ キス ハグ(2)(KUJIRA)
・ロア ~奈落のヒロイン~(1)(丘上あい)
・生徒諸君! Kids(13)(庄司陽子)
・至極の男~もう一度愛される夜(2)(ささおかえり/ボルテージ)
・吉原ボーイズとモラルガール!~フラれまくったアラサーが逆転吉原で女子の幸せお手伝いします。~(2)(鶴ゆみか)
・星降る王国のニナ(12)(リカチ)
・ハッピー!ハッピー♪ 波間信子短編集(波間信子)
・海自とおかん(3)(上田美和)
・サレ妻シタ夫の恋人たち(2)(村岡恵)
モーニングKC
・東京エンマ(1)(アカイイト)
・未熟なふたりでございますが(16)(カワハラ恋)
・サキュバス課の真面目なピュアさん(3)(如意自在)
・井口純平は今日もやれない(1)(ISAKA)
・阿南さんは出会って3秒で合体したい!(2)(松林佑)
・阿久津さんは推しに似ている(1)(白川すみれ)
・氏神さまのコンサルタント(1)(胡原おみ/西山倫子+モノガタリラボ)
KCデザート
・極婚~超溺愛ヤクザとケイヤク結婚!?~(8)(桜井真優)
・放課後ブルーモーメント(2)(旗谷澄生)
・ゆびさきと恋々(10) (森下suu)
・東千石さんのメイクアップドール(3)(ことぶきりー)
・棗センパイに迫られる日々(7)(かみのるり)
KCデラックス
・そのキスに、二言なし(1)(丹沢ユウ)
・ギャルがシルバニアファミリーを溺愛したら。#ギャルバニア(2)(岡野く仔)
・愛だけに。(9)(チカ)
・イケメン女子と金髪ショタ(2)(ふじもとまめ)
・カラダ、重ねて、重なって(8)(iko)
KC KISS
・クジャクのダンス、誰が見た?(4)(浅見理都)
・ながたんと青と ―いちかの料理帖―(11)(磯谷友紀)
・ハマる男に蹴りたい女(5)(天沢アキ)
・成瀬は恋が証明できない(1)(ナカガワパリ)
星海社COMICS
・空の境界 the Garden of sinners(12)(天空すふぃあ/奈須きのこ)
アルファポリス発行/星雲社発売
エタニティCOMICS
・極甘マリアージュ(2) 桜井家三姉妹の恋愛事情(コヨリ/有允ひろみ)
・夜毎、君とくちづけを(1)(繭果あこ/流月るる)
アース・スターエンターテイメント
アース・スター コミックス
・掃除屋のふたり(2)(完)(初野ふみの)
・転生してから40年。そろそろ、おじさんも恋がしたい。 二度目の人生はハーレムルート!?(6)(えむあ/清露ほか)
・生贄第二皇女の困惑 ~人質の姫君、敵国で知の才媛として大歓迎を受ける~(3)(水谷悠珠/かえで透ほか)
・星斬りの剣士 ~The sword fighter\'s dream~(3)(完)(酒月ほまれ/アルトほか)
・姉に言われるがままに特訓をしていたら、とんでもない強さになっていた弟~ブラコン姉に鍛えられすぎた新米冒険者、やがて英雄となる~(5)(相模映/吉田杏ほか)
・願いを叶えてもらおうと悪魔を召喚したけど、可愛かったので結婚しました ~悪魔の新妻~(7)(となりける/shiryu)
・領民0人スタートの辺境領主様~青のディアスと蒼角の乙女~(10)(ユンボ/風楼ほか)
・悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ と、ポチの大冒険(10)(荒木風羽/壱弐参ほか)
・ヤマノススメ(24)(しろ)
徳間書店
リュウコミックス
・あんアンドロどろ(5)(R-one)
・ブルターニュ花嫁異聞(3)(武原旬志)
・ひなゆり冒険記(3)(大庭直仁)
リュウコミックススペシャル
・夜光雲のサリッサ(11)(松田未来/※Kome)
リイド社
SPコミックス
・鬼役(21)(橋本孤蔵/坂岡真)
・真剣にシす(2)(盛田賢司/河端ジュン一・西岡拓哉/グループSNE)
成人向け
ジーオーティー
GOT COMICS
・(成)飲み会後の襲われセックス~初体験は強引で最悪でイキ過ぎて…~(たかみやはいり)
・(成)ハメラレ×ハマル(アシタ)
コミック新刊ラインアップはこちら
・このページに掲載されている情報の全文及び一部を他サイトへ転載することは禁止されています。また、いかなる形式であっても再配布することはできません。
・発売日は東京を基準としています。商品をお求めの際は、お近くの書店にご確認ください。
・掲載内容は予定のため、変更になる場合があります。
・リンク先のHonya Club.com商品ページは、Honya Club.comの予約受付開始以降にご覧になれます。