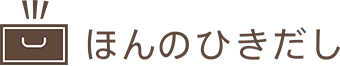- 2035 10年後のニッポン ホリエモンの未来予測大全
- 著者:堀江貴文
- 発売日:2023年06月
- 発行所:徳間書店
- 価格:1,540円(税込)
- ISBNコード:9784198656454
『2035 10年後のニッポン ホリエモンの未来予測大全』の要点
1.ChatGPTの登場は「シンギュラリティ」の到来を意味する。人間とAIの境界線は消えつつあり、AIと人間は融合していく。
2.今後はタイパ格差が進み、リモートワークで自由度の高い働き方をする人と、昔ながらの管理と制限のもとで働き続ける人との二極化が顕著になる。
3.核融合による発電が実現すれば、あらゆるエネルギー問題が解決する。
『2035 10年後のニッポン ホリエモンの未来予測大全』レビュー
テクノロジーの進化はとどまることを知らない。G7サミットでは、生成AIの利活用について、推進派と規制派とで意見が二分した。革新的なテクノロジーが席巻すると、世の中は混乱するが、やがて受け入れられていく。いま、私たちは変化の真っ只中にある。
堀江貴文氏は、本書で10年後の未来予測を試みた。「ホリエモンの未来予測大全」というサブタイトルの通り、日本経済・資産形成・AI・エネルギー問題・ビジネス・働き方・産業・社会情勢など、その切り口の多彩さに目を見張る。宇宙ロケットの開発やスマホアプリ・飲食店のプロデュースといった、幅広い事業を手がけてきた堀江氏ならではの視点に、知的好奇心がかきたてられていくことだろう。
堀江氏は、未来は予測できないものの、未来に目を凝らすことで本質が導き出されると語る。さらには、社会がいくら変化しようとも、私たちが培ってきた経験や強みは無駄にならず「人間的厚み」になると、読者を鼓舞してくれる。
シンギュラリティ到来という、人類史に残る転換点を迎えつつあるいま、世の中で何が起こっているのか? そして今後、世界はどんな次元を切り開いていくのか? そのなかで、私たちは何に注目し、どんなアクションをとるとよいのか?
本書を通じて自分なりの未来図の解像度を上げてみてほしい。価値観やライフスタイルのアップデートを楽しむためのヒントがそこにある。
『2035 10年後のニッポン ホリエモンの未来予測大全』が気になる方におすすめ
- 堀江貴文のChatGPT大全
- 著者:堀江貴文 荒木賢二郎
- 発売日:2023年08月
- 発行所:幻冬舎
- 価格:1,650円(税込)
- ISBNコード:9784344041592